
丂侾乯丂揔抧
崻挿偑70cm埲忋偁傞偺偱丄峩搚偑怺偔丄抧壓悈偺崅偔側偄偲偙傠傪慖傃傑偡丅惗堢揔壏偼20乣25亷偱偡偑丄敪夎屻偼30亷傪墇偡弸偝偱傕惗堢偟傑偡丅崻偼姦偝偵嫮偔丄廐傑偒偱墇搤偟傑偡丅楢嶌傪寵偆偺偱丄係乣俆擭偼摨偠偲偙傠偱嶌傜側偄傛偆偵偟傑偡丅丂
丂俀乯丂昳庬
丂戧栰愳乮愒宻偱崻挿偑嵟戝侾m偔傜偄偲側傝丄憪惃偑嫮偄斢惗庬乯
丂搉曈憗惗丄拞偺媨乮戧栰愳宯偱丄崻挿偑75cm偔傜偄偲抁偔丄憗惗偱嶌傝傗偡偄昳庬乯
丂桍愳憗惗丄嶳揷憗惗乮廐傑偒梡偺昳庬乯
俁乯丂嶌傝曽
丂敤偺弨旛
丂枹弉側懲旍側偳偼巤梡偼婒崻偺尨場偲側傝傑偡偺偱丄傛偔晠弉偟偨椙幙偺懲旍傪俀kg巤梡偟傑偡丅搚忞偺巁搙偼倫俫偑6.5乣7.5偑揔偟丄巁惈偑嫮偡偓傞偲懢傝偑埆偔側傝傑偡丅侾噓摉偨傝嬯搚愇奃150倗丄俛俵傛偆傝傫30倗傪巤偟丄僞僱傑偒侾廡娫慜偵偼崅搙壔惉旍椏60倗傪巤梡偟傑偡丅旍椏偼傑偒峚偺壓偵偐偨傛傜側偄傛偆偵傛偔崿崌偟丄暆60cm偺偆偹傪偨偰傑偡丅傑偨丄峩搚偺愺偄偲偙傠偼崅偆偹偲偟傑偡丅
丂僞僱傑偒
弔傑偒偼係乣俆寧丄廐傑偒偼俋寧壓弡乣10寧忋弡偱偡丅弔傑偒偱偼丄傑偔帪婜偑抶傟傞偲惗堢偑抶傟丄廐搤偺廂妌婜傑偱偵崻晹偑廫暘旍戝偟側偔側傝傑偡丅傑偨丄廐傑偒偱偼丄憗偡偓傞偲拪戜偑懡偔側傝丄抶傟傞偲姦奞偵傛傝墇搤偟側偔側傝傑偡偺偱丄傑偔帪婜偵偼拲堄偟偰偔偩偝偄丅僞僱傑偒傪偡傞慜偵堦拫栭棳悈偵偮偗偰傾僋敳偒偡傞偲敪夎偑傛偔偦傠偄傑偡丅偆偹偺忋偵愺偄峚傪愗偭偰侾cm偔傜偄偺娫妘偵忦傑偒偟傑偡丅僑儃僂偺僞僱偼岲岝惈側偺偱丄暍搚偼敄偔偟傑偡丅
娫堷偒
丂杮梩侾乣俀枃偺崰偲俁乣係枃偺崰偵娫堷偒偟丄嵟廔偺姅娫傪10cm偔傜偄偵偟傑偡丅恾偺傛偆偵梩暱偑抁偔丄梩偑峀偑傞傛偆偵怢傃偰偄傞姅偼婒崻偑懡偄偺偱娫堷偒傑偡丅

丂捛旍丒搚婑偣
丂惗堢婜娫偑挿偄偺偱丄旍愗傟偝偣側偄傛偆偵偟傑偡丅捛旍偺帪婜偼戞侾夞栚偑杮梩俀乣俁枃弌偨崰丄戞俀夞栚偼杮梩俆乣俇枃偺崰偱偡丅偄偢傟傕懍岠惈偺崅搙壔惉旍椏傪侾噓摉偨傝20倗丄偆偹尐偵巤偟偨屻拞峩偟丄惗挿揰偑搚偵杽傑傜側偄掱搙偵搚婑偣偟傑偡丅
丂廂妌
丂弔傑偒偼俋乣12寧偵廂妌偱偒丄廐傑偒偼梻擭偺俇乣俈寧偵廂妌偟傑偡丅栚埨偲偟偰偼崻宎偑1.5乣俀cm偵側偭偨崰偐傜廂妌傪巒傔傞傞偲傛偄偱偟傚偆丅僑儃僂偺杧傝曽偼丄側傞傋偔崻晹傪姰慡偵孈傝庢傞偨傔丄懁柺傪僗僐僢僾側偳偱偱偒傞偩偗怺偔孈傝壓偘丄愜傜側偄傛偆偵拲堄偟側偑傜堷偒敳偒傑偡丅
丂傑偨丄梩偑20cm偔傜偄偵側偭偨傜丄梩僑儃僂偲偟偰傕棙梡偱偒傑偡丅
挋憼
丂敤偵幬傔偵婔楍偵傕暲傋偰搚偱暍偄傑偡丅姦偝偵嫮偄偺偱丄搥傜側偗傟偽俁乣係寧偺拪戜偡傞崰傑偱挋憼偱偒傑偡丅
丂係乯丂昦奞拵杊彍
丂楢嶌偡傞偲栦塇昦丄崟斄昦傗僱儅僩亅僟偺旐奞偑戝偒偔側傝傑偡偺偱丄係乣俆擭偼偁偗傑偡丅傾僽儔儉僔偵偼儅儔僜儞擕嵻乮廂妌慜俈擔傑偱乯偱杊彍偟傑偡丅僐僈僱儉僔偑敪惗偟偨傜丄偱偒傞偩偗曔嶦偟丄嶦拵嵻偺巊梡傪峊偊傑偡丅

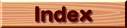
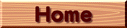
丂擔杮撈摿偺栰嵷偱丄掅壏偵嫮偄丅楢嶌傪寵偆偺偱丄係乣俆擭偼偁偗傞丅慇堐幙傪懡偔娷傓栰嵷偲偟偰媟岝傪梺傃偰偄傞丅