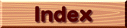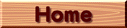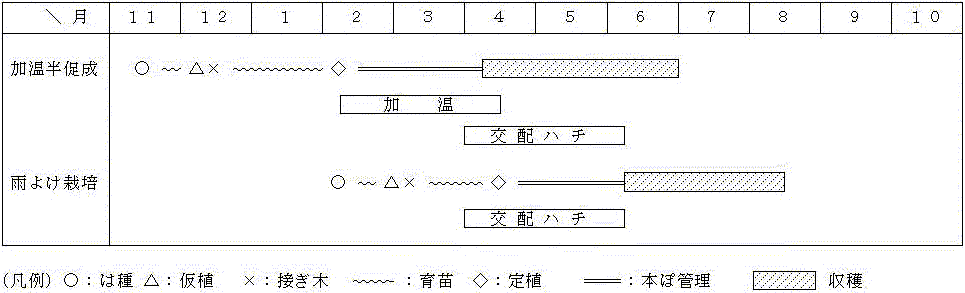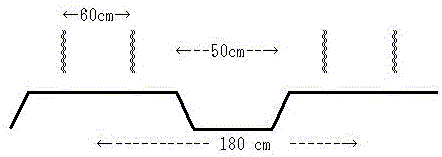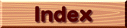
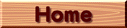
半促成トマト 、雨よけトマト
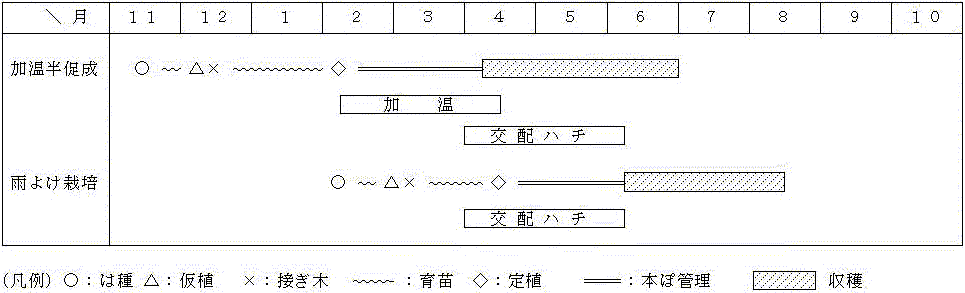
1. 品種例
穂木:(半促成)ハウス桃太郎、桃太郎ヨ-ク
(雨よけ)桃太郎8、桃太郎T93、桃太郎ヨ-ク 台木:影武者、アンカーT、がんばる根
土壌病害の発生状況(青枯病、根腐れ萎凋病)や穂木とのTMV抵抗性型の適合性に注意して台木を選定する。 根腐れ萎凋病優勢ほ場 影武者
青枯病優勢ほ場 アンカーT、
土壌水分の多いほ場 がんばる根(浅根性である)
※ 桃太郎ヨークは根腐れ萎凋病(J3)に抵抗性である。
2. 目標収量 半促成 9,500 kg/1,000㎡
雨よけ 8,000 kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
過繁茂とならないよう、元肥の量、灌水量、灌水方法等で樹勢をコントロールする。
また、3段花房以降の草勢を弱めないよう、草勢を見ながら遅れることなく1回目の追肥を行う。
4. 技術内容
(1) 育苗
① 用土の準備
(ア)は種床
市販の培土では場合は必要ないが、自家調達する場合は臭化メチル燻蒸剤で消毒しておく。
接ぎ木する場合は、育苗箱50箱あたり400リットル
程度必要である。セルトレイを利用する場合は 128穴トレイ46枚当たり専用培土200リットル程度必要である。
は種床は、8㎡(電熱温床)程度が必要である。
(イ)移植床
鉢上げ用土には、通気・排水のよい保水性のよい用土を3m3(1m3で4号ポット1,000
鉢分)準備しておく。
自家製用土を作成する場合は、排水性の良い田土と完熟堆肥を1:1の容量比で混合する。
土壌消毒を行った後、用土1㎡あたり、細粒868を2kg程度、苦土石灰
1.5kg、過燐酸石灰3kgを施用し、pH6.5、EC 0.7ms/cm(1鉢当たり窒素200mg、リン酸 500~750mg、カリ200mg)に調整しておく。
調整後に、再度pH、ECを確認する。
(ウ)電床
は種床、移植床とも 3.3㎡あたり 250Wとなるよう電熱線を設置する。は種床では床温を均一にするため、温床の外側は 内側よりも電熱線の間隔を狭くする。
移植床ではポットの下に電熱線がくるように配線する。
本ぽ1,000㎡あたり播種床8㎡、育苗床200㎡設置する。
事前に通電し、適温まで上昇するのを確認しておく。
② たねまき
半促成栽培:11月中旬
雨よけ栽培:2月上旬
台木は、呼び接ぎでは穂木と同時~3日早く、幼苗接ぎでは穂木と同時~1日早く、は種する。
は種床は育苗箱やとろ箱、セルトレイを利用する。
は種までに十分潅水し、適温に加温しておく。
育苗床はトンネル被覆を行い、夜間は保温シートやコモをかけて保温する。
穂木、台木とも、
播種量3,000粒(40~60ミリリットル )、
条間6cm、株間2cm、深さ0.5cmに条まきする。 セルトレイでは1粒/穴に播種する。
は種後は乾燥防止のために新聞紙をかけておくが、発芽が始まればすぐに取り除く。
育苗中の温度管理は下表を参考に電熱線の設定やトンネル、ハウスの開閉を行う。
高温管理すると第1段花房の着生節位が上がる。
特に幼苗接ぎでは、播種後しっかり潅水して、地温28℃を保って発芽を揃える。発芽が揃えば、最低気温を16~18℃に下げる。本葉展開時には14℃くらいに管理して、胚軸の徒長を防止する。
播種後15、20日目に液肥1,000倍液の追肥を行う。
は種床の温度管理
生育ステージ
|
気温(℃) |
地温(℃) |
昼温 |
夜温 |
昼温 |
地温 |
播種~ 発芽
~ 子葉展開
~ 本葉2.5枚
|
25~30
25~26
23~24
|
25~30
15~16
14~15
|
28
28
25~26
|
23
18~20
17~18
|
③ 鉢上げ
ポリポットは土入れ後、電床に並べておき、あらかじめ灌水して加温しておく。
呼び接ぎでは播種後20日前後、本葉
1.5~2葉期に4号ポリ鉢の中央に台木を鉢上げする(セルトレイ利用苗も同様に鉢上げする)。
穂木は、呼び接ぎの場合は接ぎ木しやすいように台木の2~3cm横に、幼苗接ぎでは鉢の端に鉢上げする。 本葉2~3葉期が第1段花房の分化期となるので、順調に活着させる。
④ 接ぎ木
(ア)呼び接ぎ
播種後30~35日前後、本葉3~4葉時に接ぎ木する。 接ぎ木後は、鉢に灌水して乾燥を防ぎ、遮光資材と保温資材等で遮光密閉したビニールトンネル温床内に並べて温度、湿度を確保する。
接ぎ木当日は、温度25℃、霧吹きで湿度90%を確保し、暗黒とする。その後は順次湿度を下げ、光線を当てて順化させる。
接ぎ木10日後くらいで穂木の胚軸をつぶし、萎れなければ、穂木の胚軸の切断を行う。
(イ)幼苗接ぎ(チュ-ブ接ぎ)
播種後20~25日、胚軸径1.8~2.3mm、本葉2~2.5葉期 に、接ぎ木支持具(スーパーウィズ等)を用いて行う。
台木と穂木の太さを揃えて活着率を向上させる。
接ぎ木支持具には内径の異なる種類(1.4、1.7、1.0、2.3
mm)があり、胚軸径に応じたものを用いる。チューブの内径を胚軸径より少し細くして、チューブと胚軸が密着するものを選ぶ。
接ぎ木の2~3日前より水分を控えめにして、やゝ締め気味の苗に仕上げておく。
接ぎ木前に十分潅水した後、台木の子葉上の第1節間を30度の角度に切断してチューブをさし込み、穂木も子 葉上の第1節間を30度に切断し、台木の切断面と密着するようにさし込んで接ぐ。接合面の方向とチューブの向きに注意する。
接ぎ木後は鉢に灌水し、遮光資材と保温資材等で遮光密閉したビニールトンネル温床内に並べて温度、湿度を確保して活着させる。
接ぎ木当日は、25~28℃、霧吹き等で湿度90%を確保し、暗黒とするが、その後は順次光線を当てて(1~5klux、雨天時の日射量程度)、3~8日間で順化させる。
⑤ 育苗中の管理
(ア)温度
鉢上げ時には、夜温を25℃まで上げ、活着を促進させる。活着後は、徒長を防ぐため、徐々に夜温を下げ定植時までには12℃前後とする。窓あき果、チャック果等奇形果を防止するため、夜間12℃以上を確保できるよう保温管理を行う。
外気温の低いときには、荒風を苗に当てないように換気には注意する。
移植床の温度管理
生育ステージ
|
気 温(℃) |
地 温(℃) |
昼温 |
夜温 |
昼温 |
地温 |
本葉2.5~6枚
本葉7枚~定植
|
20~22
18~20
|
12~15
10~12
|
22~24
15以上
|
13~15
13~15
|
(イ)養水分
地温がすぐに戻るよう、晴天日の午前中に灌水する。 夕方には鉢土表面が乾く程度の水量で徒長を防ぐが、順調に花芽を分化させるため、極端な乾湿差をつけない。
後半の肥切れは生理障害の原因となるので、葉色等を見ながら遅れないように液肥の
800倍、あるいは緩効性肥料を鉢あたり2~4粒程度施用する。
(ウ)ずらし
接ぎ木後は葉が重ならないよう2回に分けて鉢を広げ、通風と採光を図る。最終は、3.3㎡あたり50鉢程度とする。
(エ)育苗時の病害虫防除
害虫防除のため、ハウス開口部をネットで被覆しておく。定植時に病害虫を持ち込まないよう、育苗期には防除を徹底しておく。
(2) 本ぽ準備
半促成栽培では2層カーテンと加温設備を準備する。
土壌病害虫の発生に応じ、土壌消毒する。
①
施肥(施用量は土壌診断により加減する)
施肥例
(kg/1,000㎡)
|
|
肥 料 名 |
成 分 |
基 肥 |
追 肥 |
熟成堆肥
有機石灰
苦土重焼燐 |
|
2,000
120
40 |
|
CDU化成
速効性化成肥料
液 肥
|
12-12-12
16-10-14
10-4-8
|
100
(全層)
20
(待肥)
|
20
20/回
|
|
|
<参考>緩効性肥料を用いた施肥例(kg/1,000㎡)
|
|
肥 料 名 |
成
分 |
基
肥 |
追
肥 |
被覆緩効性肥料(140日タイプ)CDU化成速効性化成肥料液 肥
|
20-0-13 12-12-1216-10-1410-4-8
|
100(全層)
80(全層)
20(待肥)
|
10/回
|
|
|
※
熟成堆肥、有機石灰、苦土重焼燐は前表と同量
②
畝立て、栽植密度
2,400株/1,000㎡、3.3㎡あたり8本程度とする。
畝幅180cm、条間60cm、株間45cmの2条千鳥植えとするが、畝幅、株間はハウスの間口に合わせて調整する。
(3)
定植
定植7日前には中央に灌水チューブを設置し、透明フィルムでマルチングし、地温18℃以上を確保しておく。 定植までに植え穴に十分灌水しておく。
定植適期苗は育苗日数70~80日(半促成)、60~70日(雨よけ)程度である。
第1花房1番花の開花始めに、花房を通路側に向け、晴天日の午前中に定植する。開花した株から順に定植して行く。
浅植えとし、深植えし過ぎないようにする。
日中の気温が28℃以上になれば換気を行う。夜間最低温度は12℃以上に管理する。
(4)
灌水
過繁茂を避けるため、定植直後~活着まではホースで 株元に灌水する。
活着後は、第3花房開花前後まで、灌水を控えめにして根を深く張らせる。生育初期の低地温時の潅水時には、潅水後2~3日は最低夜間温度を2~3℃高めにして、地温の低下を防ぐ。その後は、草勢、果実の肥大、天候、気温に応じて1株1回あたり0.5~1.5リットル程度をチューブ灌水する。
(5)
誘引
主枝1本仕立てとする。支柱は2m間隔に立て、支柱 の上に番線を張り、つりっこ等の市販の誘引具を設置し、誘引する。主枝の先端が支柱から出ないよう、横へずらしながら誘引する。
(6)
温度管理
午前中は25~28℃とし、28℃以上は換気を行う。午後は18~23℃とする。
最低夜温は、活着までは12℃以上を保ち、第1花房ホルモン処理時以降は10℃以上に管理する。
生育初期の低地温時の潅水後2~3日は最低夜間温度を2~3℃高めにして、地温の低下を防ぐ。地温の目安は15℃以上が望ましい。また、この時期は湿度が高くなりやすいので、夕方にカーテンを閉める前に暖房機の運転を始めて除湿し、灰色かび病の発生を防ぐ。
生育後半は高温となるが、結実不良を防ぐためハウスサイドを全開とするなどして、できる限りハウス内の気 温を下げるように工夫する。特に生長点、開花花房付近の通気をよくして、30℃以上には上げない。夜温を20~23℃を目安として管理する。
また梅雨明け後は、マルチの上に敷き藁を行い、地温の上昇抑制と青枯病の発生の抑制をはかる。
(7)
追肥
草勢に応じて追肥の時期、量を調整する。
桃太郎ヨークは早めの追肥を心掛ける。
1回目の追肥は1段花房がピンポン玉大時に液肥料でN成分で2kgを目安とし、草勢が強い場合は潅水のみとする。
2回目は3段花房開花時に化成肥料をN成分で3kg施用し、中~後期の草勢維持をはかる。
以後、4~7段の各段開花期にN成分で1kgを目安とに液肥で追肥する。
施肥参考例のように元肥に緩効性肥料を相当量施用している場合は、追肥はほとんど必要ないが、草勢が弱い場合は追肥する。
(8)
整枝、摘果、摘葉、摘芯
主枝1本仕立てとし、腋芽かきは遅れないように、晴天日に行い、夕方までには傷口が乾くようにする。
収穫が済んだ果房下まで摘葉し、光線の透過、通風をよくし、病害虫予防を図る。
着果数は、1段花房が4果、2段花房以上が4~5果に摘果する。乱形果や肥大不良果等異常果はピンポン玉大までに早めに除去する。草勢のバランスを考え、弱い場合は、3果にして草勢を回復させる。
8~9段(雨よけでは7~8段)花房を着けたらその上2葉を残して早めに摘芯する。
(9)
着果促進(ホルモン処理、交配バチ)
1~2段花房は、ホルモン処理を行い、確実に着果させる。トマトトーンの場合の濃度は、
20℃以下は
60~
80倍、
20~25℃は
80~120倍、
25℃以上は130~150倍、とする。
中段以降、草勢が強く高温で空洞化が心配される場合はジベレリン10
ppmを混用する。
処理時期は1花房2~4花咲きで、1回処理とする。2度がけすると生育障害を引き起こすので、注意する。
3段花房以降はマルハナバチを利用できるが、バイトマークによる訪花痕を調べ、マルハナバチが活動しているか確認しておくこと。
初期肥大はホルモン処理と比べるとやゝ遅れる。
マルハナバチの寿命は40~50日程度なので、栽培期間中に交配バチを交換する。殺虫剤を使用する場合は、剤により散布後導入可能日数が異なるので十分注意する。
(10)病害虫防除(県病害虫防除基準に基づいて防除する)
①
アブラムシ
②
タバココナジラミ、オンシツコナジラミ
③
マメハモグリバエ
④
ヒラズハナアザミウマ
育苗期に十分な防除を行い、苗から本ぽに持ち込まな いようにする。また、施設周辺の雑草等に発生源を作らないよう注意するとともに、ハウスの開口部に寒冷紗を張り、外部からの侵入を防止する。
定植時の殺虫剤(粒剤)の植え穴施用で初期防除が可能であるが、マルハナバチを使用する場合は、訪花忌避の影響が高いので、定植後20~30日間はホルモン処理で着果させる。
⑤
葉かび病
外気温が低いため換気できない春先や梅雨時期に湿度が高くなると発生が多くなる。換気やマルチングによってハウス内の湿度の低下を図る。
⑥
灰色かび病
着果後の花弁が発生源となるので取り除く方がよい。 花抜けを良くするために、ホルモン処理のタイミングを早過ぎないよう、また最低夜温は8℃以下にならないようにする。
加温機を早朝や曇雨天時に稼働させて施設や樹の結露時間を短縮し、湿度を低下させることで予防する。
ホルモン処理時に薬剤の混用も可能であるが、濃度、散布回数等防除基準を守る。
内張りカーテンに除湿、透水性のある割繊維資材(PVAフィルム等)を使用すると発病抑制効果がある。
⑦
青枯病
地温上昇とともに発生が多くなる。抵抗性台木の利用 とハウス内気温を30℃以上にしないよう換気し、マルチ上に敷き藁する等、地温を28℃以上にしない管理が必要である。
⑨
疫病
窒素過多や20℃くらいの低温多湿環境で発病が助長される。換気を十分に行い、多湿環境にしない。
(11)主な生理障害(原因と対策)
①
空洞果
ホルモン処理により着果させるため種子が成熟せず、果実心室内のゼリー部の発達が悪くなり、心室内部に隙間が発生する症状である。果実全体が角張り、商品性が低下する。
幼果時の高温による果実肥大のアンバランスによるため、ホルモン剤を高濃度、高温時(30℃以上)、蕾処理すると空洞化が発生しやすい。また老花苗定植によっても助長される。
対策としては、高温時のホルモン処理は、夕方涼しくなってから行う、開花当日の花に処理し、蕾処理は避ける、ジベレリン10
ppmを加用する等である。
②
チャック果、窓あき果
チャック果は、果面全体あるいは一部分にチャック状の線が見られる症状で、窓あき果は果面の側面に大小様々な穴があく症状である。どちらも子房に雄しべがつい たまま肥大し、その部分がコルク化するために起こるもので、どちらも原因は育苗時の低夜温(12℃以下)および育苗中の窒素過剰、水分過剰等、栄養過剰による花芽分化の異常によるものと考えられている。
対策は、育苗中の夜温に注意し、12℃を下回らない、育苗土を適正に調整し窒素過剰とならないようにし、花芽分化をスムーズに行わせることである。
③
尻腐れ果
カルシウムの吸収不良による欠乏症状で、果実の花痕部を中心として黒褐色となり商品価値がなくなる。高温、乾燥期の幼果に多く発生する。
また、チッソ肥料(特にアンモニア態窒素)が多いとカルシウムと拮抗するため、発生しやすい。
対策として、有機質肥料や緩効性肥料を基肥に使用し、石灰資材の施用で土壌酸度を適正にする。土づくりや水管理によって根を深く張らせて表層の高地温の影響を少なくする。ハウス内の気温、地温を下げる。土壌の過乾、過湿を避ける水分管理を行う。
また、カルシウム資材を生長点や花房(蕾、花、幼果)と周辺の葉に散布すると発生を軽減できる。
(12)収穫、出荷
果実温が上昇するまでに収穫を完了させる。高温時には着色が進みやすいので、やゝ早めに収穫する。
(改田
茂典)