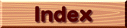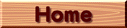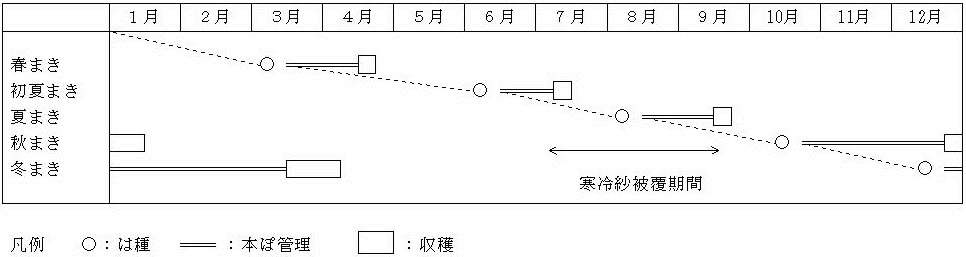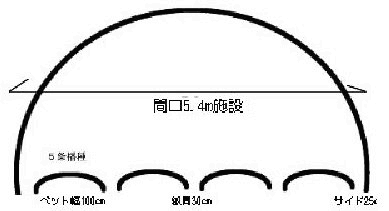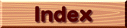
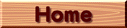
ほうれんそう 周年栽培
1. 必要な施設条件
(1) ほ場条件
排水が良好な砂壌土が適する。
転作の場合は隣の水田から水が流れ込まないこと。
(2) 設備条件
間口 5.4~6.0mのパイプハウス。
水の便がよいこと。
鮮度保持ができる冷蔵施設、トラクター、管理機等。
2. 品種例
(1) 春まき用品種
抽苔しやすい時期なので、晩抽性品種を選ぶ。
べと病R4が発生している場合、耐病性の品種を選ぶ。
適合品種:アクティブ、サンバ、サンライト
(2) 夏まき用品種
高温と長日照により、発芽不良と抽台の発生が多くなる。晩抽性かつ耐暑性の強い品種を選ぶ。
7月上~中旬はいずれの品種も最適とはいえない。
適合品種:アクティブ、おかめ、(7月以降)マルス
(3) 秋まき用品種
気温が下がり、日長も短くなる時期で、もっとも栽培のしやすい時期である。品質重視で品種を選ぶ。
適合品種:アトラス、アンナ、ラルゴ
(4) 冬まき用品種
気温が低く生育が遅くなる時期である。生育速度が比較的に速い品種を選ぶ。
適合品種:リード
3. 作付け体型の考え方
(1) 1回当たり播種面積
収穫適期の日数と調整能力に見合った面積にする。
1日あたり調整能力 600束、収穫適期幅3日、の場合
200g×600束×3日=360 Kg、収量が1,200kg/1,000㎡ とすると、
1回当たりのは種は1,000㎡×360kg÷1,200kg=300㎡
(2) 他の品目との組み合わせ
夏期の栽培はほうれんそうには不適であり、この時期に耐暑性の強い品目を組み合わせた体系をとってもよい。
品目は、ネギ、こまつな等。
4. 目標収量
販売量1,000kg / 1,000㎡ (機械まき、一斉収穫)
5. 栽培のポイント
(1) 発芽揃いを確保する
発芽率を高め、生育をそろえるために、プライマックス処理(又はネーキッド処理)を施した種子を用いる。 プライマックス処理をした種子は、発芽までの乾燥に弱いので、発芽が揃うまではこまめに灌水をする。
ただし、発芽が不良となる夏期は、無処理の種子を冷蔵催芽処理をして播種する。
冷蔵催芽処理は、20℃程度のやゝ低温で一晩浸漬させる。その後、むしろなどの上で陰干し、10%程度発芽したところで播種する。この場合、機械まきはできないので手まきするが、厚播きにならないように注意する。
(2) 高温対策
盛夏期は、施設内温度の上昇を防ぐために黒寒冷紗等をハウスの天井外側に被覆する。
畝は高めに立て、地温の低下につとめる。
(3) 芽立ち後の立ち枯れ防止
本葉展開後は株が軟弱になりやすいので灌水は控える。 後半、乾燥するようであれば畝間に灌水する。
(4) 土壌消毒による連作障害の回避
ほうれんそうを周年栽培すると、萎凋病が多発するので、夏期に太陽熱消毒や薬剤消毒により土壌中の菌密度をさげる。
6. 技術内容
(1) 本ぽ準備
① 施肥例 (1,000㎡あたり Kg)
肥料名 \作型 |
夏まき |
秋まき |
冬~春 |
完熟堆肥 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
有機石灰(新作時) |
200 |
200 |
200 |
ようりん |
|
60 |
80 |
固形化成肥料 |
100 |
120 |
100 |
化成肥料
|
|
80
|
60
|
② 畝立て
5.4m間口の施設では下図のように畝をたてる。
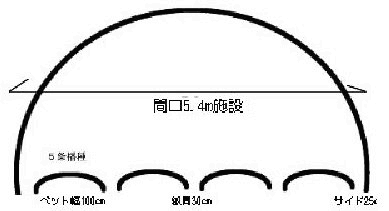
耕起の前に十分灌水し、1週間程度経ってからトラクタを入れる。
整地は通常3行程で行う。
荒起こしは主に残滓と雑草の処理を目的とし、トラクタのロ-タリ-速度をやゝ速く、耕耘を浅くする。
整地はロ-タリ-速度を1段落とし、深く耕耘する。このとき同時に元肥を施用する。
共にパイプ付近まで耕耘する必要があり、ロータリーはできればセンタードライブ方式のものが望ましい。
畝立ては管理機を用いる。土跳ね羽根を調節して通路幅を30cmにする。待ち肥として速効性肥料を施用する場 合は、畝を立てる前に散布する。
(2) 播種
種子は1,000㎡あたり、機械まきの場合プライマックス種子で6万粒(2袋)、手まきの場合普通種子で4リットル程度準備する(種子の処理は栽培のポイント参照)。
条間20cm、畝あたり5条まきにする。株間は次表のようにする。時期により株間を変えるのは、株張りが違うためである。
播種前に土に十分に水を含ませる。
作付け時期ごとの株間
|
株 間 |
密 度 |
備 考 |
春・秋まき |
5.5cm |
70株/㎡ |
|
夏まき |
5.0cm |
75株 |
ばらまきも可 |
冬まき |
6.5cm |
60株 |
|
(3) 灌水
灌水はチュ-ブ、ホ-スまたは常設の塩ビ管を用いる。
塩ビ管の場合は150~200cmの高さに固定し、必ず水抜き用のパイプ・コックをつける。
なお、6m間口以上のハウスでは、両端まで灌水ができないので、2本設置する。
灌水は必ず早朝に行う。やむを得ず夕方に行う場合は、パイプにたまった水を抜いてから行う。
初夏~初秋は発芽がそろうまで乾燥させないようにこまめな灌水が必要であるが、灌水ムラがないように手灌水が望ましい。
(4) 収穫の要点
草丈が25~28cmになったら収穫を始める。草丈が30cm以上となり、フィルム袋から葉がはみ出すと市場評価を 下げる。特に夏期の生育は早く、実質的な収穫適期は3日程度である。
収穫は品温が低い早朝に行い、収穫後は速やかに予冷庫に移して萎れを防ぐ。直接冷風がかからないように、コンテナをドンゴロスなどで覆っておく。収穫後の葉水は流通中の腐りの原因となるのでしない。
また、施設内で調整作業をするのも、高温期には品質保持の点で問題である。
(5) 防除
① 耕種的防除
ほうれんそうは栽培期間が短く、使用できる薬剤が少ない。そのため、薬剤に頼らずに、次のような耕種的防除を併用する。
| 対 策 | 効 果 |
サイドネット被覆 |
害虫の飛び込み防止 |
太陽熱消毒 |
土壌病原菌の密度低下 |
紫外線カットフィルム |
病害虫の不活性化 |
② 薬剤防除
薬剤を利用する場合は滋賀県病害虫防除基準に基づき使 用する。
7. 省力化と軽作業化のポイント
(1) 調整作業の効率化
袋詰め作業に補助具(下敷き)や回転作業台を活用するとよい。補助具は厚めの軟質ビニールや雨トイを利用 したものなどが利用されている。
回転作業台は、3人以上で組み作業をする場合に有効で、下葉取りを済ませた収穫物をかごに入れ直したり、運ぶ手間を省くことができる。
(2) 真空播種機の利用
ベルト式の機械まきよりも播種精度が高く、生育のそろいが良好になる。
(3) 作業姿勢の改善
ほ場作業はかがみ姿勢が多く、腰や膝に対する負担が大きい。作業椅子や運搬車の利用で軽作業化を図る。
8. パッケージ
鮮度保持フィルム等の機能性フィルムを用いると市場評価が高い。
また、初夏~秋は予冷出荷が望ましく、他品目と組み合わせた予冷施設の活用を図りたい。
出荷は段ボール箱、縦詰めが一般的である。
(藤澤 悟 )