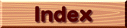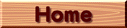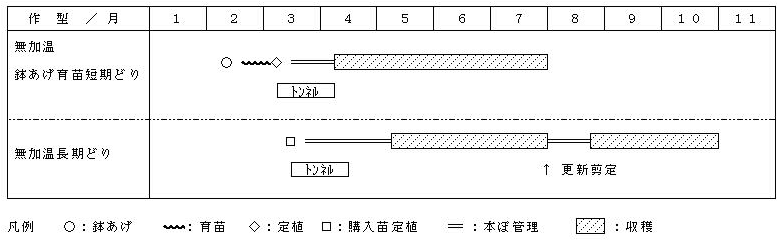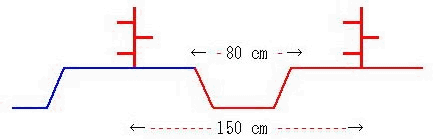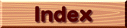
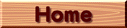
半促成なす
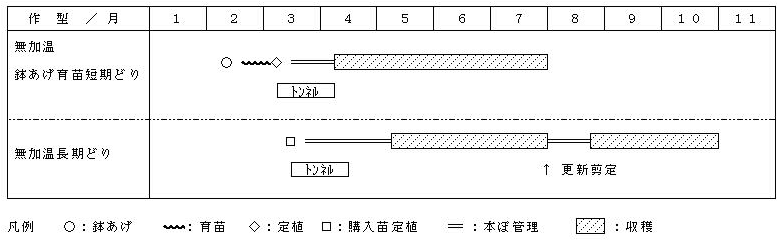
1. 品種例
穂木:千両、千両2号
台木:赤ナス
トルバムビガー(半身萎凋病等発生の場合)
2. 目標収量
鉢あげ短期どり: 6,000 ㎏/1,000㎡長期どり:10,000 ㎏/1,000㎡
3. 栽培のポイント
(1) 適正な基肥投入と温度確保による初期管理
(2) 整枝、摘葉の徹底
4. 技術内容
(1) 育苗(鉢あげ育苗する場合)
① 鉢土準備
鉢土は苗1,000本に対し約1m3用意する。
鉢あげの2週間前に田土1m3に対し完熟堆肥300㎏をよく混ぜ込み、臭化メチルでくん蒸消毒を1週間行う。
くん蒸後、3~4日間ガス抜きを行い、苦土石灰 1.5kg、細粒868を1.5 ㎏加え、よく混合したものを鉢土用土として用いる。
② 育苗床準備
日当たりの良いハウス内に温床を作り、電熱線を㎡ あたり80wの割合で配線する。
温床は苗1,000本当たり 40㎡必要で、上記の用土を12cm径ポリポットに詰めて並べ、トンネルを掛けられるようにしておく。
鉢あげの1~2日前から通電し、鉢を暖めておく。
③ 鉢あげ、育苗管理
2月上旬に、本ぽ1,000㎡あたり購入苗(7.5cmポット)1,000鉢を導入し、12cmポリポットに鉢あげする。
温床をトンネルで被覆し、定植まで20~30日育苗する。
育苗中の温度管理の目安は
鉢あげ~順化 日中25~27℃、夜間16~18℃
順化時 日中23~25℃、夜間14~15℃
朝は早目にトンネルを開き、太陽光線を取り込み、夕方は早い目に閉め、夜間の保温に努める。
徒長を防ぐため、葉が混み合う前に温床を広げてずらしを行い、 かん水は控えめにする。
本ぽ定植1週間前からは苗の順化のため夜間の温度を14℃位まで下げ、苗の硬化をはかる。
なお、苗床での病害虫防除は徹底して行い、本ぽに持ち込まないように注意する。
(2) 本ぽ準備
① 基肥施用
連作ほ場では、作付け前に必ず土壌分析を実施し、結果に応じて基肥施用量を決定する。
前年中に完熟堆肥、鶏ふん、苦土石灰を施用し、全耕しておく。
定植の1週間前に残りの基肥を施用し、整地後かん水チューブを設置し、充分にかん水した後透明マルチをかけ、地温の上昇をはかっておく。
②施肥例(㎏/1,000㎡)
|
肥料名 |
成分 |
基肥 |
追肥 |
|
完熟堆肥 |
|
2,000 |
|
|
苦土石灰 |
|
120 |
|
|
乾燥鶏ふん |
|
200 |
|
|
BMようりん |
0-20-0 |
60 |
|
|
蒸製骨粉 |
4-22-0 |
60 |
|
|
CDU化成 |
12-12-12 |
100 |
|
|
速効性化成肥料 |
16-10-14 |
30 |
|
|
油かす |
5-2-1 |
|
60×2 |
|
NK化成
|
16-0-20
|
|
30×6
|
③畝立て、栽植密度(1,000株/1,000㎡)
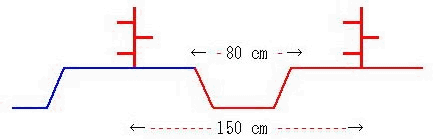
(3) 定植
定植は風のない晴天日を選んで行う。
前日に植穴を掘っておき、ミナミキイロアザミウマ防除のため、県防除基準に基づき殺虫剤(粒剤)を1穴に1~2g施用し、トンネルをかけて地温を上げておく。苗にも前日に充分にかん水しておく。
株間50cm、畝の中央に1条植えにする。深植えにならないように、鉢土を畝表面より高く植え付ける。
植付け後充分にかん水し、仮支柱をして固定する。
1畝ごとに定植が終わればトンネルをかける。
(4) 温度管理
初期生育促進のため、内カーテンおよびトンネルで比較的高温に管理し、日中は25~30℃とし、30℃以上になれば換気する。夜間は16~18℃の確保に努める。
トンネルの除去はハウス内の夜温が12℃以上確保できる時期を目安とし、カーテンも14~15℃程度あれば閉じないでおく。
4月に入ると外気も上昇するので、ハウスサイドの開閉により温度調節する。
6月以降は夜間もハウスサイドを開放する。
(5) 光線管理
同化作用促進のためにも、早朝から積極的に太陽光線を取り込むようにする。
トンネルは早めに開き、カーテンも必要温度が確保できれば開くようにする。曇雨天日でも採光することが大切である。
(6) かん水
果実の発育促進、品質向上のため生育期間中は充分な水分を供給する。かん水量、回数は畝の土壌水分をマルチをめくって確かめながら決定し、急激な乾湿がないようにする。
夏期には水分要求量も多くなり、水分不足は樹勢の低下、つやなし果の発生、ハダニの多発原因となるので注意する。
チューブかん水で不足する場合は、夕方に畝間にかん水を行う。
(7) 整枝・誘引・摘葉
① 主枝の整枝と誘引
主茎と1番花の下から発生する強い側枝2本を主枝とし、3本仕立てにする。
誘引は充分に採光できるように主枝を配置する。
支柱を畝の両肩に2mおきに立て、針金(16番線)を 地上1mと2mの高さに2段に張り、3本の主枝を2本と 1本に振り分けて誘引する。
主枝は針金に直接しばりつけるか、またはビニールひも で引っ張って誘引する。
主枝の先端が上の針金のところまで伸びれば、摘心して 側枝の発生を促す。
② 側枝の整枝
側枝に蕾が1つ現れれば、その上1葉残して摘心し、1ヵ所に複数の花が着いた場合は弱い花を摘み取る。
太く、勢いがある側枝では上段の花も残して摘心する。側枝の果実を収穫する際は、同時に切り返し剪定を行い、孫枝の発生を促す。
③ 摘葉
黄化した葉や主枝を覆う大きい葉は摘葉し、株の中心部および株元まで光線が当たるようにする。
葉は一度にたくさん取らないようにする。
(8) 追肥
生育期間が長く、栄養生長と生殖生長が同時に行われるので、全期間を通じて肥料を効かせるよう、速効性の化成肥料を主体に、適宜、追肥する。
なお、栄養状態が良い株では花は大きく、花弁の色は濃紫色で、長花柱花である。開花位置は枝の先端から15~20㎝で、花の先の葉数は4~5枚である。
栄養状態が悪いと、花は小さくなり、開花数が減少し、短花柱花が多くなる。開花位置は枝の先端に近くなり、花の先の葉数も1~2枚になる。
(9) 着果促進
低温期において確実に着果させるために、ホルモン剤を使用する。
ホルモン剤はトマトトーンを使用する。希釈倍率については、処理時の温度、湿度、樹勢によって変える。
当日または前日に開花した花に、家庭用スプレー等で希釈液を1花あたり0.6㏄ずつ噴霧する。この時、希釈液が葉や茎、生長点にかからないよう注意する。
また、重複処理を避けるため、希釈液1リットル あたり食紅を1~1.5g溶かしておく。
ホルモン処理濃度(トマトト-ン)
月 |
3 |
4 |
5 |
6 |
希釈倍率
|
25~30
|
40
|
50
|
60~70
|
樹勢の強い場合は、やや濃いめにする。
(10)花抜き
ホルモン処理後、幼果に花弁が付いていると灰色かび病が発生しやすく、着色不良果が生じやすくなるので、必ず花弁を抜き取る。
花弁はあまりに早く抜くと幼果に傷を付けることもあるので注意。
(11)更新剪定
生育が進み混み合ってくると、採光、通風が悪く、病害虫の発生や樹勢が衰えてくるので、7月下旬に主枝3本とも、基部の葉を2~3枚残して、強く切り取り、枝の更新を図る。
(12)主な病害虫防除(県病害虫防除基準を参考にする)
① ハダニ:高温乾燥が続くと発生しやすい。こまめに観察し、初期防除に努める。更新剪定時の防除が効果的である。薬剤抵抗性がつきやすいので、グル-プの異なる薬剤でのロ-テ-ション使用に心がける。
② 灰色かび病:花弁抜きが不十分だと発生しやすい。
③ うどんこ病:高温乾燥期に発生しやすい。過繁茂の株に出やすい。発生初期の薬剤防除が効果的である。
④ ミナミアザミウマ:苗からの持ち込みが多いので、定植直前に十分防除しておく。ハウス側面に寒冷紗等を張り、侵入を防ぐ。
(13)主な生理障害(原因と対策)
① 石ナス果
原因:日照不足、摘葉のしすぎ、養水分不足、ガス害等による同化養分の不足、または低温、樹勢の低下、栄養過多による果実への転流不足。
窒素の多施用、水分過多などで発生が多い。
対策:保温、採光を図り、同化と転流を促進する。
養水分の適正管理により樹勢を調整する。
発生したら、ホルモン処理濃度を高くし、確実に着果させる。
② ガク割れ果(裂果)
原因:高濃度、高温時のホルモン処理。
未熟花への処理や重複処理でも発生する。
窒素肥料の多施用により石灰欠乏症の花にも発生しやすい。
対策:ホルモン剤の適正処理と、水分、肥料の適正な管理による石灰欠乏症の防止。
③ つやなし果(ボケナス)
原因:果実肥大期における水分の転流不足。
土壌水分の不足、根の機能低下による吸水不足。長雨の後の晴天時等に発生しやすい。
対策:かん水。土壌物理性の向上(保水、排水性向上のための資材投入)。
④ 着色不良果
原因:日照不足、採光不良、ビニールの汚れ等による光線透過率の低下、紫外線カットフィルム等の使用。花抜き作業の不徹底。
対策:整枝、摘葉による採光性の向上。花抜きの徹底。フィルムの洗浄、使用被覆資材の検討
⑤ デコボコ果(ブク果)
原因:高温下や樹勢が弱い時の高濃度ホルモン処理。
対策:ホルモン剤濃度の調整、樹勢回復。
⑥ 奇形果(キンチャク果、双胴果など)
原因:低温時の強い切返し。高濃度ホルモン処理など。
対策:ホルモン剤濃度の調整。
⑦ 日焼け果
原因:果実面の結露や直射日光の影響。
急激な温度上昇による過剰な蒸散による相対的な水分不足。
対策:早朝(日の出頃)換気によって結露の防止、温湿度の急激な変化を小さくする。
また、実が葉の影になるように、十分な灌水によって葉を繁らせる。
(川村 藤夫、近藤 博次)