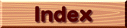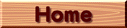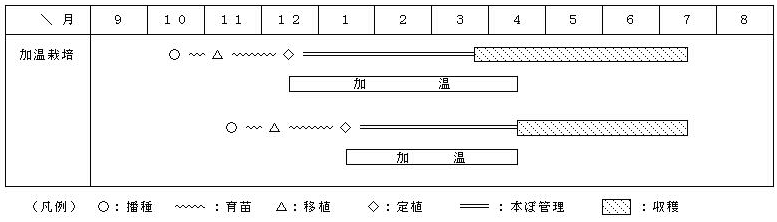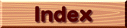
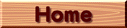
少量土壌培地耕 半促成トマト
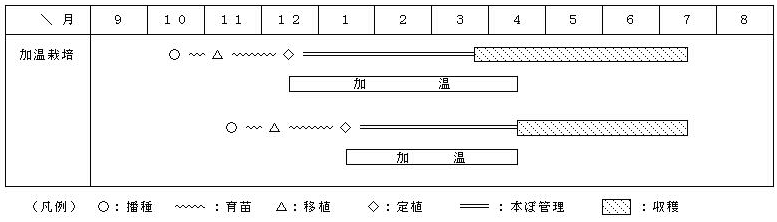
1. 品種例 ハウス桃太郎、桃太郎ヨーク
2. 目標収量 9,500 kg/1,000㎡
3. 技術内容
(1) 育苗
① 用土の準備
(ア)は種床
ピートモスと砂を1:1で混合し、は種床用土にする。
(イ)鉢土
1,000㎡あたり3m3の用土が必要である。
排水の良い田土と堆肥を1:1の割合で混合し、臭化 メチルで土壌消毒を行う。
7〜10日間消毒した後、用土1m3あたり細粒868を4kg、苦土石灰2kg、過燐酸石灰2.5kg施用し、pH 6.5〜7、EC0.6〜0.7 ms/cmに調整する。
② 電熱温床
本ぽ1,000㎡あたり温床 120㎡必要である。 3.3㎡あたり250Wの電熱線を設置する。
育苗床はビニールトンネル被覆を行い、夜間はむしろや保温シートをかけておく。
③ たねまき
必要種子量は60ミリリットル。
トロ箱等を利用し、は種までに適温に加温しておく。
条間6cm、1.5cm間隔、深さ5mmにまき、覆土する。
は種後十分灌水し、濡れ新聞をかぶせる。
4〜5日で発芽してくるので、発芽後すぐに新聞紙を とり、徒長させない。
④ 間引き
片方の子葉が小さいもの、子葉が貧弱なもの等、奇形 株は早めに間引く。正常な苗を痛めないよう注意する。
⑤ 温度管理
次表を目安にサーモスタットの設定、トンネルやハウスの開閉を行う。また、光が十分あたるように管理する。
発芽までは高温管理し、発芽後はすぐに夜温を低めにして徒長を防ぐ。その後は徐々に管理温度を下げ、本ぽ定植への順化を行う。極端な低温は芯どまりをおこし、特に6葉期までの低温は窓あき果やチャック果の発生が多くなるので最低温度に注意する。
育苗中の温度管理の目安
生 育 ス テ ー ジ |
昼 温 |
夜 温 |
は種 〜 発芽
〜 子葉展開
〜 本葉2.5枚
〜 本葉6枚
〜 定植
|
25〜28℃
25℃前後
20〜23℃
20〜22℃
18〜20℃
|
25〜28℃
16〜17℃
14〜15℃
12〜13℃
10℃前後
|
⑥ 水管理
発芽し、子葉が展開したら条間に溝をつけ、そこへ灌水する。頭上灌水は徒長の原因になるので行わない。
鉢上げ後は晴天日の午前中に灌水を行う。鉢上げ直後はショックを和らげるため、ハウス内で暖めた水で潅水するのが望ましい。乾き過ぎないように水管理を行うが、多灌水は根が傷んだり、徒長をまねくので注意する。
⑦ 鉢上げ・ずらし
本葉2〜2.5枚時に12cmポリポットに鉢上げする。 ポリポットは、土入れ後電床に並べ、あらかじめ加温しておく。熱効率を考えて、隙間ないように並べる。
鉢上げは、奇形株を除きながら、根を乾かさないよう行う。鉢上げ後は十分灌水する。
生育が進み、葉が触れ合うまでにポットをずらす。最終間隔は12cm×12cmとする。
(2) 本ぽ準備
システム設置は、少量土壌培地耕の項を参照。
2層カーテンおよび暖房設備を準備・点検しておく。
(3) 定植
定植前にベッドに充分給水しておく。
株間60cmで、2条千鳥植え(2,000本/1,000㎡)。
土耕と同様に、品種にあわせた開花状態で定植し、若苗は初期生育が旺盛になり、開花しすぎたものは老化苗になる。天気の良い日の日中の暖かい時間帯に定植するのが望ましい。
(4) 培養液管理
大塚A処方または山崎トマト処方を用いる。 大塚A処方1単位はEC 2.2、山崎トマト処方1単位はEC1.2である(調整方法は抑制トマト参照)。
培養液の管理基準は次表のとおりで、樹勢をみながらEC値を変更する。
ステ−ジごとのEC値と給液量
生育ステージ |
大塚A処方 |
給液量/株 |
定植後〜活着
活着〜定植後20日
〜定植後60日
〜第3花房開花
〜収穫終了14日前
〜収穫終了
|
水 の み
EC 0.5
EC 1.2
EC 1.2
EC 1.5
水 の み
|
0.5リットル/日
1リットル
1.5リットル
2リットル
2リットル
2リットル
|
各ステージごとにECを調整する(ECコントローラ)pH 6.5に設定する(pHコントローラ)。
給液は、低温期は午前10時から、高温期は午前7時から開始する。1回の給液量は400〜500ミリリットル /株とする。
(5) 温度管理
定植後活着までは最低温度を13℃以上に保ち、第1段花房のホルモン処理(交配)終了までは10℃以上に管理し、それ以降は8℃以上に管理する。最高気温が28℃以上になれば換気を行う。
35℃以上の高温では空洞果、着色不良果が発生し、5℃以下の低温では、チャック果等奇形果が発生するので温度管理に注意する。
(6) 誘引
ベッド木枠に沿って、支柱(径20mm、長さ2m)を2m間隔に立てる。支柱は後作にそのまま使用できる。 支柱に針金を張り、市販の誘引器具を付け、先端が支柱からはみ出ないように横へずらしながら誘引する。
(7) 整枝
① 芽かき
一本仕立て、腋芽は早めにとる。ハサミ等の利用は病気の蔓延の恐れがあるので、手で取る。
② 摘芯
目標段数は10段である。花房が開花したら花房の上の葉を1〜2枚残して摘芯する。芽かき同様早めに行う。
③ 摘果
1段花房は4果、2段以上は4〜5果を残し、乱形果や肥大不良果を摘果する。ピンポン玉までに摘果する。
④ 摘葉
収穫が終わった花房以下の摘葉し、通風よく、誘引ひもをずらしやすくする。樹勢が強くなりすぎた場合は状況に応じて花房上下の葉を1/2〜1/3切り取る。
(8) 着果促進(ホルモン処理、交配バチ)
① ホルモン処理を行う場合
花房に3〜4花開花時にホルモン処理を行う。曇天時、高温時のホルモン処理や重複処理は障害の原因になる。 また、生長点にかかると先端葉が柳葉になる。
ホルモンの濃度(トマトトーン)
花 房 段 |
濃 度 |
第1段
第2段
第3段
第4段以降
|
60倍
80倍
100倍
120倍
|
中段以降の高温時に空洞果の心配がある場合は、ジベレリン10ppmを加える。
② 交配バチを利用する場合
マルハナバチはの寿命は約40日で、栽培期間中に2〜3回購入する。低温期はハチの活動が不十分で、4月以 降の利用が望ましい。
また、農薬散布が制限され、薬剤ごとにマルハナバチへの影響期間が異なる。散布前に必ずチェックする。
1巣箱の交配面積は 1,000㎡で、ハウスの設置状況によっては巣箱を移動して利用してもよい。
低温期の低段花房は確実に着果させるためにホルモン処理との併用が望ましい。
ハチの活動は花柱の一部が褐変するので(バイトマーク)確認できる。
ハチの寿命の終わった巣箱を処分しておく。
(9) 病害虫防除
灰色かび病を予防するため花弁抜きを励行する。
幼果時の花弁抜きはヘタの周りが褐変するので、ピンポン玉以上になってから行う。
通路にマルチを敷き、ハウス内湿度を下げて、病害発生を予防する。
少量土壌培地耕では地表面が乾燥し、露出している培土も少ないので湿度が下がり、病害が発生しにくい。
(10)主な生理障害(原因と対策)
① 空洞果
(ア)原因
老化苗の定植、植え痛み、着果過多、開花不揃い時の高ホルモン処理、高夜温、窒素過多等が原因で、果肉部とゼリー部の発育に差ができ、その間に隙間ができる。
(イ)対策
適期苗定植し、植え痛みのないようにする。
摘果を行い、適正数を着果させる。
過繁茂にならないよう、培養液管理を行う。
ホルモン処理は濃度を守り、花房に3〜4花開花したときに処理を行い、つぼみ時に処理しない。
ハウス内温度を上げないよう、こまめに換気を行う。
② チャック果・窓あき果
(ア)原因
育苗土の窒素過多、6葉期までの低温管理、植え痛み、本ぽでの低温管理、過繁茂等が原因で子房が肥大する過程で花器の分化がスムーズに行われず、子房の表面に雄ずいが癒着したまま肥大し、その部分がコルク化してチャック状、穴あき状になる。
(イ)対策
育苗土のECは0.6〜0.7 ms/cmに調整し、窒素過多にならないようにする。
特に6葉期までの温度管理に注意し、最低温度が12℃を下回らないように管理する。
老化苗や植え痛みさせないよう定植する。
定植後は最低温度が10℃を下回らないよう管理する。
過繁茂にならないよう、培養液管理を行う。
(峯 憲一郎)