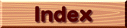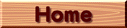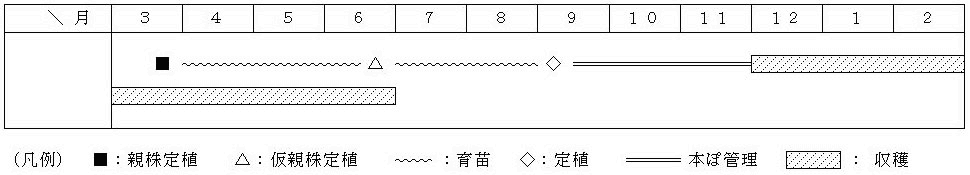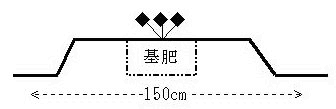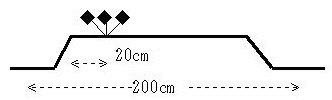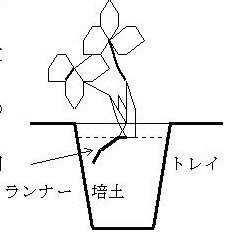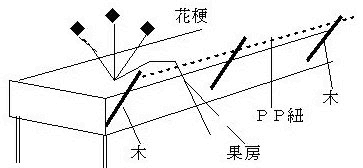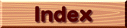
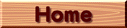
少量土壌培地耕 促成イチゴ
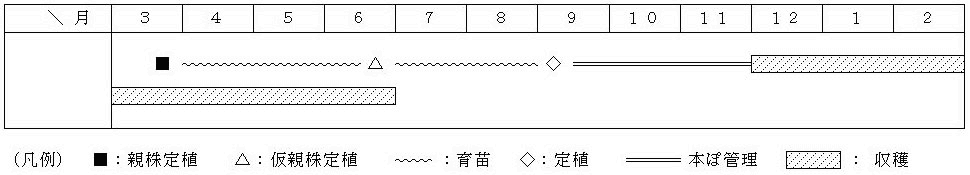
1. 品種 女峰
2. 目標収量 3,500 kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
(1) 本ぽ定植は9月5日前後(花芽分化前定植)とする。
(2) 育苗、本ぽとも定植は深植えしないように注意する。
(3) 花梗が折れやすいので、防止対策を施す。
4. 技術内容
(1) 無仮植育苗
① 親株床の準備
(ア)施肥例(kg/60㎡、100株)
肥料名 |
成 分 |
基 肥 |
苦土石灰 |
|
7.0 |
ようりん |
0-20-0 |
2.7 |
普通化成
|
8-6-8
|
2.0
|
※苦土石灰は全面施用、ようりん、普通化成は株元に施用。
(イ)親株床の畝立て(栽植苗数:100株/本ぽ1000㎡)
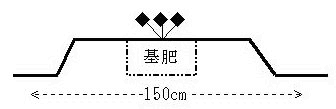
(ウ)親株定植
前年の10月下旬〜3月中下旬にウイルスフリー苗を本ぽ1,000㎡ 当たり 100株を株間40cmに植え付ける。定植 後十分に灌水する。
4月上旬に殺虫粒剤を畝全面に散布し、寒冷紗(#300)で被覆する。
親株1株から第1子苗を5株確保する。
② 仮親株床の準備
(ア)施肥例(kg/400㎡、500株)
肥 料 名 |
成 分 |
基 肥 |
苦 土 石 灰 |
|
40 |
よ う り ん |
|
15 |
普 通 化 成
|
8-6-8
|
15
|
※肥料は全て全面に施用する。
(イ)仮親株の畝立て(栽植苗数 500株/本ぽ1,000㎡)
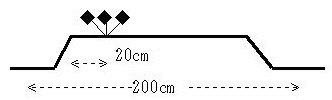
(ウ)仮親株の定植
6月下旬に親株から採った第1子苗(太郎苗)を本ぽ 1,000㎡当たり 500株、株間40cmに畝の片側に植える。
定植後、活着までは十分に灌水する。
イチゴは乾燥に 弱いので堀取り後は根を乾かさないようにすぐに植え付ける。
太郎苗から発生しているランナーは取り除いておく。
(2) ナイアガラ育苗
① 親株定植
定植方法、施肥法は無仮植育苗に準じるが栽植密度を120株/本ぽ1,000㎡と多くするため施肥量を増やす。
② 仮親株定植
定植時期;6月15日、栽植密度;600株/本ぽ1,000㎡
第1子苗を本ぽベットに株間25cm、1条に定植する。
灌水はOK-F-1の2,500倍液を1日2回(午前10時、午後3時)給液する。
灌水量は60ml/回・株に給液量を調節する。培地の土質により乾きかたが違うので萎れるようならば1回あたりの灌水量を増やす。
③ 採苗
定植予定日から遡り30日前(8月上旬)にイチゴ専用のセルトレイ(45穴)に苗を採る。
採苗は本葉2枚から3枚苗で行う。採苗の時には仮親株側のランナーを2cm程度残す。 これを培土に差し苗を固定する。
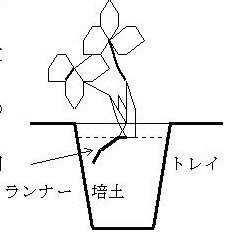
④ 寒冷紗被覆・灌水
採苗後から活着まで(約1週間)は黒寒冷紗で3重被覆を行い、この間は常に培土が十分湿っているように水管理を行う。
活着後は寒冷紗を1枚ずつはずしていき、徐々に光に慣らしていく(2週間程度で完全にはずしてしまう)。
遅くまで掛けておくと、徒長苗になるだけでなく、根鉢の発達が悪くなる。
(3) 本ぽ管理
① 本ぽ定植
(ア)時期 9月5〜10日
(イ)定植適期苗の状態 本葉3〜4枚の苗
(ウ)裁植密度
株間20cm、2条千鳥植え(約7,800株/1,000㎡)
親株の反対側に花が咲くので、親株側のランナーを3cm程度残し目印とし、これをベットの内側に向け、クラ ウンの半分程度が埋まるように定植する。
② 花梗折れ対策
春期になると果梗が長くなり、ベンチ木枠のところで折れやすい。木枠に添うように植えると折れにくい。
また、下図のようにPP紐等で花梗を受けるとよい。
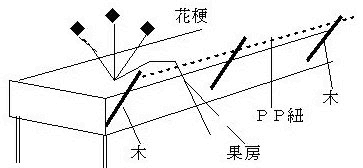
③ 養液管理
(ア)灌水(水量調整)
事前に、0.4リットル/分・ベッド1m に水圧を調節しておく。
(イ)施肥例(OKF-1の希釈倍率 )
生育ステ−ジ |
希釈倍率 |
定植後から花芽分化
花芽分化後
頂花房収穫後
腋花房収穫以降
|
3,000 倍
2,000
3,000
2,000
|
☆ 定植〜花芽分化はエバホウソ3,000倍を加用する。
☆ 9月中旬に花芽分化を確認し、希釈倍率を変更する。
☆ 開花期〜頂花房着果期に葉色が低下する場合には、そのときの養液濃度より500倍濃度を上げて葉色を戻す。
☆ 排液は養液タンクに戻し、再利用する。
(ウ)灌水方法
時 期 |
灌 水 方 法 |
定植〜
マルチ張り後2日 |
1日2回(10時、15時)
各1分間給液する(※1) |
マルチ張り
3日目以降 |
1日1回(午前10時)
1分間給液する。 |
12月上旬以降、排液が多くなってきたら |
1日1回1分間給液する。
2日給液、1日休む。 |
3月中旬以降排液が
少なくなってきたら |
1日1回1分間給液する。
毎日給液 |
4月下旬以降、排液が更に少なくなってきたら |
1日2回(10時、15時)
各1分間給液する(※1)
|
6月中旬、収穫終了予定の10〜15日前
|
1日2回(10時、15時)
各1分間、水のみ給液(※1)
|
※1;曇天日等、15時に培土が十分に湿っている場合には、午後の給液を中止する。
④ 温度管理
生育段階 |
昼間 |
夜間 |
定植から出蕾期 |
26℃〜27℃ |
12℃ |
出蕾から開花期 |
26℃〜27℃ |
10℃ |
開花から収穫期
|
28℃
|
5℃
|
冬期夜間は最低気温5℃以上の確保は難しいが、0℃以下にならなければ大きな問題はない。夜温が低下した場合には、翌日の日中を高い温度に管理する。
⑤ マルチ張り
10月中旬に、黒マルチを掛ける(95cm幅のマルチを半分に切る)。株が大きくならないうちに早めに行う。
⑥ 保温
10月下旬頃から最低気温が12℃以下になるので夕方にハウスサイドを閉め保温をする。日中は28℃以上になれば換気する。
11月上旬から夜間、内張りカーテンにより保温を図る。
⑦ 換気
カーテンを閉め始めると、早朝には湿度が高くなる。温度が低い場合にも、湿度が高く株が濡れているときには、朝に10〜15分間ハウスサイドをあけて換気する。
⑧ 炭酸ガス施用
カーテン保温開始以降、炭酸ガス発生剤を利用し、炭酸ガスを施用して光合成を促進する。施用期間(開花期以降)は最高温度を28℃と高めに設定し換気を控える。
⑨ 交配
開花が始まったら(10月下旬)1棟に1群導入する。1群で 500㎡の交配が可能である。
農薬散布する時はミツバチをハウスの外に出してから行う。散布後は各薬剤のミツバチに対し影響のなくなる日数になってから戻す。
⑩ 芽かき
定植から頂花房開花までは頂芽1本に管理し、頂花房開花以降は頂芽とその直下の腋芽の2本に管理する。
収穫開始以降は、常に2花房程度に管理すると収穫の切れ間が少ない。
⑪ 摘葉・ランナー取り
定植〜10月中旬は新葉の展開が早いので、老化葉は株元からかき取る。1回の摘葉で1株2葉までにする。
10月中旬以降は、新葉の展開が遅くなってくるため黄化した葉や枯死した葉のみかき取る。
収穫期以降は、収穫の終わった果房をかき取る。
3月上旬以降は新葉の展開が早くなり、株元が混み合うのでこまめに葉かきする。
定植から開花期までと3月以降はランナーが発生するので付け根から除去する。
⑫ 摘花(果)
各果房の咲いている花の数を12〜15花になるように弱い花や乱形果を摘花(果)する。
また、花数が少なくても後から咲いてくる弱い花は摘み取る。
(4) 主な病害虫対策
① 育苗 炭そ病が重要病害であり、本ぽへ持ち込まないように、育苗床で徹底的に防除する。雨よけ施設を利用して育苗するのが望ましい。
② 本ぽ ミツバチへの影響を考え、開花までに、アブラムシ、ハダニ、うどんこ病を防除しておく。
灰色かび病予防のため、出来るだけ換気に努め、枯死葉は早めに取り除く。
(中村 嘉孝、中野 学 )