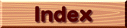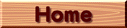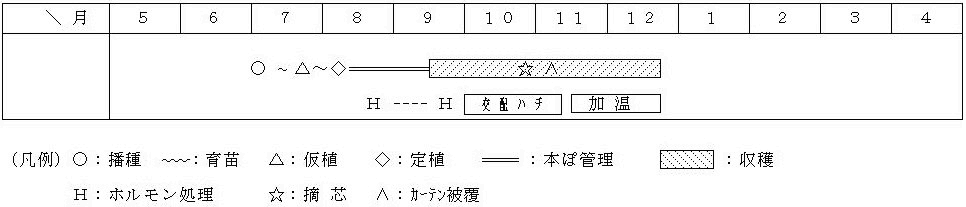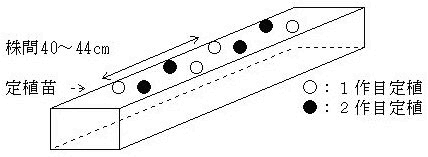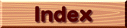
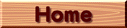
少量土壌培地耕 抑制トマト
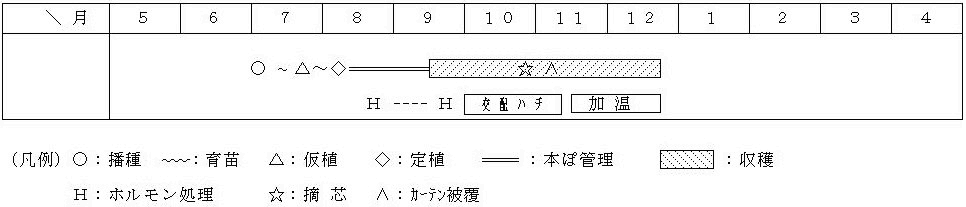
H:ホルモン処理 ☆:摘 芯 ∧:カーテン被覆
1. 品種例 桃太郎、桃太郎8、桃太郎ヨ−ク
2. 目標収量 9,000㎏/1,000㎡
3. 栽培のポイント
(1) セル苗も利用できるが、若苗は定植後の生育が旺盛となりやすいので、肥培管理に注意する。
(2) 高温期から低温期に向けての生育となるため、生育に応じた給液や培養液管理を行う。
4. 生理・生態的特性
(1) 発芽の適温
発芽適温は25℃前後で、幼苗期の生育は根部で28℃、地上部では25〜30℃のため、高温期の育苗のため換気に十分注意する。
(2) 生育期の適温
昼間20〜30℃、夜温11〜17℃で良好な生育を行う。花蕾は35℃以上の高温が続くと落果が多いほか、果実のリコピンの生成が抑えられて黄味が強くなる。
5. 技術内容
(1) 育苗
① 播種床の準備
ポット育苗:育苗箱(33×60×5㎝程度)当たり8リットル程度の用土が必要で、市販培土を利用するか、水管理がしやすい用土(例:土、川砂、バ−ミキュライト、ピートモス、それぞれ同量を混合)を準備する。
ポット用土は、直径8㎝のポリ鉢が 0.3リットル、9㎝鉢で 0.4リットル必要なため、鉢数に応じて用土を準備する。病害回避のため、防除基準に基づき土壌消毒を行う。
セル育苗:市販の排水性が良好な培土を購入し、覆土にはバーミキュライトを用いる。トレイ当たり 3.5〜4リットルの培土が必要で、トレイに詰める前に適度な湿り気を与えておく。
② 種子の準備
本ぽ1,000㎡当たり、ポット育苗では50〜60ミリリットル、
セルトレイ育苗では40ミリリットル準備する(20ミリリットル は 約1,600粒)。
③ たねまき
(ア)ポット育苗:育苗箱に条間5〜6㎝、種子間隔 1.5㎝程度に播種し、本葉1.5〜2葉期にポットに仮植する。
原則として接ぎ木は不要である。
ポットは直径8〜9㎝のものを用い、育苗期間は30日程度とする。生育に応じてズラシを行い、軟弱徒長にならないよう注意する。
(イ)セル育苗:市販の50穴トレイを用いる。
播種前にトレイに十分潅水した後、1粒まきする。
④ 管理
播種後は十分灌水し、発芽まで新聞紙などをかける。また、ハウス内が高温となるため、30℃以上にしないよう寒冷紗などで日中遮光し、ハウスの換気につとめる。
(2) 本ぽ準備
① 用土の準備
新規作付の場合:用土は田土か畑土を用い、肥料の残効がなく、病害の心配のない土壌を用いる。
栽培ベッド(底面24㎝と側面12㎝で、モミガラ厚3㎝、培土7㎝の場合)の培地量は、ベッド1m当たりモミガラが約7リットル、培土が17リットル必要である。
防除基準によりクロ−ルピクリンまたは臭化メチル剤で土壌消毒を行い、十分ガス抜き後に栽培床に詰める。
培土の連用の場合:培土に塩類が集積している場合は、水を十分かけ流して除塩してから定植する。
② 栽植密度
株間40〜44㎝の2条千鳥植えとする。
栽植密度は 2,800〜3,100株/1,000㎡。
③ 定植法
培地の連用の場合は、前作の株と株の間に所定の穴を開け、千鳥植えとする。とくに高温時は根鉢が乾きやすいので、定植後は1日数回の手灌水を行い、活着を促す。
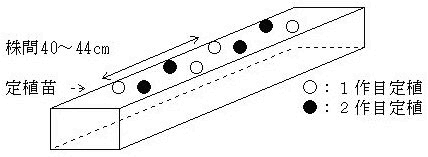
(3) 培養液の種類
山崎処方トマト用1単位濃度(原水が水道水の場合、 EC値1.2〜1.3mS/cm)を基準とする。山崎処方は大 塚ハウス2号をA液、同 3、5、6、7号をB液とする。 原液は最高 100倍までとし、高い濃度で2つの原液を 混ぜると沈殿が生じる。
トマト用100倍原液のつくり方
処方 肥 料 の 種 類 水100リットル 当たり
山崎処方 A液 大塚2号 3.6㎏
トマト1単位 B液 大塚3号 4.0㎏
5号 50g
6号 2.5㎏
7号 0.8㎏
大塚A処方 A液 大塚1号 15.0㎏
1単位(参考) B液 大塚2号 10.0㎏
(4) 給液
定植後は、活着促進のため株当たり 500ミリリットルを目安に、1日2〜3回給液する。
給液量は生育に応じて増やし、第2花房開花期頃には株当たり1リットルを3〜4回、第3花房開花期頃からは2リットル を目安に5〜6回に分けて給液を行う。
高温期における給液時刻は、定植後しばらくは午前中を重視して10、13時の2回、生育最盛期は7、9、11、13、17時とする。低温期になれば施用回数を減らし、日中を 中心に行う。
(5) 培養液管理
定植1週間までは水のみを給液する。その後は山崎処方でEC値 0.6 mS/cm程度から施用を始め、生育状況に応じて 1.0m S/cm程度とする。着果期(第3花房開花期)以降、草勢が弱まる時期には、1.5m S/cm程度まで高める。
(6) 培養液循環施用
給液量は給液量の3割程度が排液タンクに戻るのを目安に設定する。
培養液の消毒や肥料要素毎の調整は特に行わないが、培地に肥料が蓄積し、排液のEC値が給液を上回る場合は培養液の濃度を下げる。
(7) 温度管理
土耕栽培に比べ草勢はおとなしいが、高温が続く場合は初期生育が旺盛となりやすいので、ハウス内の温度管理には十分注意し、換気につとめる。
(8) 栽培管理
① 支柱立て
支柱は栽培床より15〜20㎝程度離れたところに立て、支柱上段に鉄線を張り、支柱に固定する。
② 誘引
栽培床が地面によりやゝ高くなるので、下位段では通路側に誘引し、その後は生育に合わせて斜め誘引する。
③ 摘葉
地面からベッド面まで30㎝以上あるため、風の通りは土耕栽培に比べて優れている。しかし、樹勢が旺盛となり、下段部分が込み合うようになれば、採光と風通しをよくするために、黄化葉を中心に摘葉を行う。
④ 摘果
中段までは果房当たり4〜5個、冬の弱光、低温期や樹勢が弱い場合は、果房当たり3〜4果程度に摘果し、上物率の向上を図る。
⑤ 摘芯
収穫目標段数の花房が出蕾したら、花房上位2枚の葉を残して摘芯する。
⑥ ホルモン処理
ハウス内の気温が30℃を越えると花粉の稔性が低下する(25℃で 100%、30℃で 37%)。第1果房の2〜3花が開花した時点でホルモン処理により確実に着果させる。トマトトーン120〜150倍液を晴天日の午前中に処理する。
⑦マルハナバチの利用
ハウス内が高温となる8〜9月(33度℃以上で活動を 停止)は利用できないのでホルモン処理を行う。気温が低下する10月頃よりマルハナバチを利用する。
(9) 除塩対策
栽培終了2週間前から、水のみで栽培することで、培地の余剰肥料成分を無駄なく利用できる。排液EC値が原水とほぼ同じになれば除塩は完了である。除塩せずに次作を栽培すると生育障害が起こるので注意する。
(10)病害虫防除
土壌伝染性の病気の培地への侵入を防ぐため、外部か らの持ち込みに注意するとともに、汚染土壌の飛散防止を含めて、通路等にマルチを被覆する。
その他の病害虫防除は従来の栽培法に準ずる。
(11)生理障害
若苗では定植直後の生育が旺盛となりやすく、1段果房開花前後から下位葉にカリ欠に類似した症状を発生することがある。
トマトは、生育の前半にN、P、Kの吸収が盛んで、特に高温時では栄養のバランスがくずれた場合に発生しやすいので、極端な若苗の定植を控える。
(12)栽培床の太陽熱消毒
前作に土壌病害が発生した場合は、必ず太陽熱消毒を行う。実施は夏期の高温時で、ハウス内が60℃以上に保持できれば、培地温が55〜60℃で6〜7時間保たれ、10〜15日間処理することで土壌病菌の死滅が期待できる。
培地に潅水して十分湿りを与えた後、栽培床を透明ビニールで覆い地温を上昇させる。
(大谷 博実)