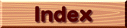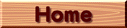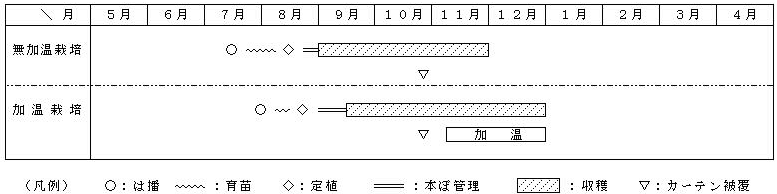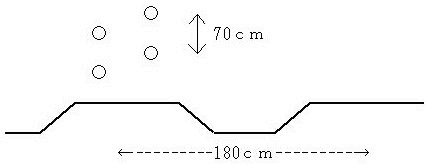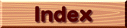
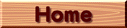
丂 梷惂僉儏僂儕
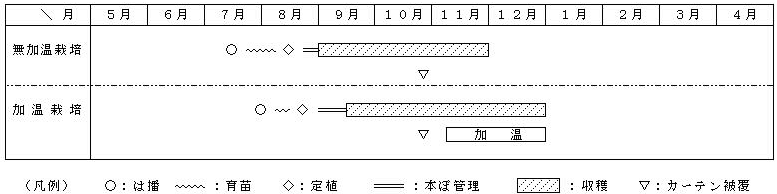
丂
丂
侾. 昳庬椺
丂丂曚栘丗傾儞僐乕儖10丄傾儖僼傽愡惉丄側偍傛偟
丂丂戜栘丗桨蔬皦_棾丄傂偐傝僷儚乕丄捶徊膱陭P 摍
丂丂丂丂丂乮僽儖乕儉儗僗戜栘乯
丂
俀. 栚昗廂検丂丂丂8,000kg乛1,000噓
丂
俁. 嵧攟偺億僀儞僩
(1) 梷惂嵧攟偱偼崅壏婜偺偼庬偺偨傔丄壏搙娗棟丄悈娗棟偵拲堄偡傞丅傑偨丄戞侾夞栚偺捛旍偑憗偡偓傞偲棳傟壥偑憹壛偡傞偺偱丄巤旍僞僀儈儞僌傪奜偝側偄傛偆偵偡傞丅
丂
(2) 惗堢弶拞婜乮崅壏婜乯偺姺婥偲丄惗堢屻婜乮掅壏婜乯偺曐壏丒壛壏傪抶傟側偄傛偆偵峴偄丄庽惃堐帩偵搘傔傞丅
丂
係. 媄弍撪梕
(1) 堢昪
丂丂僉儏僂儕偺敪夎揔壏偼28乣30亷丄寵岝惈偱埫強偱偺敪夎偑憗偄丅敪夎帪偵偼庬巕廳偲摨偠偔傜偄偺悈暘傪媧廂偡傞偺偱丄姡憞偟側偄傛偆偵拲堄偡傞丅
嘆 偼庬彴偺弨旛
丂丂偼庬彴搚偼丄悈娗棟偺偟傗偡偄搚乮愳嵒丄僺乕僩儌僗丄丂僶乕儈僉儏儔僀僩傪崿崌偡傞乯偲偡傞丅旍椏偼擖傟偢偵丄丂塼旍摍偱懳墳偡傞丅
嘇 庬巕検
丂丂曚栘丄戜栘偲傕懙偭偨椙昪傪妋曐偡傞偨傔偵丄怉晅偗梊掕杮悢偺俀妱憹暘傪梡堄偡傞乮1,800棻乛1,000噓乯丅
嘊 偼庬
丂丂攄庬帪婜偼俈寧拞弡乣俉寧忋弡傑偱丅崅壏婜偺堢昪偲側傞偨傔丄姺婥偑廫暘壜擻側僴僂僗偱峴偆丅
丂丂偙偺帪婜偼傾僽儔儉僔側偳偺奞拵偺旘棃偑懡偄偺偱丄僴僂僗僒僀僪柺偵姦椻幯傪挘傝丄奞拵偺怤擖傪杊偖丅
丂丂偼庬偼僩儘敔側偳傪棙梡偟丄曚栘偼俆乣俇cm亊俀乣俁cm丄戜栘偼俇cm亊俁乣係cm娫妘偺忦傑偒偲偡傞丅戜栘偼曚栘偲摨擔傑偨偼侾擔屻偵偼庬偡傞丅
丂丂偼庬屻偼廫暘偵偐傫悈偟丄怴暦巻偱暍偭偰姡憞傪杊偖丅丂敪夎屻偡偖偵怴暦巻傪庢傝彍偔丅
嘋 偼庬彴娗棟
丂丂敪夎傑偱偼拫栭偲傕27亷慜屻偵曐偮偑丄敪夎屻偼搚忞悈暘傪峊偊丄宻傪懢偔堢偰傞丅愙栘慜偼偐傫悈検傪梷偊丄屌傔偺昪偵偟偰偍偔丅
嘍 敨搚偺弨旛
丂丂敨搚偵偼丄朿擃偱捠婥惈偲悈傕偪偑椙偔丄昦奞拵偺怱攝偺柍偄暔傪梡偄傞丅搚忞徚撆傪峴偆応崌偼巊梡偡傞俀廡娫慜傑偱偵峴偄丄廩暘偵僈僗敳偒傪偟偰偍偔丅
亙椺亜丂揷搚丂丂丂丂丂丂丂丗500丿馁
丂丂丂丂姰弉懲旍丂丂丂丂丂丗500丿馁
丂丂丂丂嬯搚愇奃丂丂丂丂丂丗侾kg
丂丂丂丂夁椨巁愇奃丂丂丂丂丗侾kg
丂丂丂丂壔惉旍椏乮俉俇俉乯丗侾kg
嘐 愙偓栘
丂丂曚栘偺杮梩弌巒傔乮杮梩偺戝偒偝偑500墌峝壿掱搙丄偼庬屻俈乣俉擔乯丄戜栘偺巕梩揥奐帪偵屇愙偓傪峴偆丅
丂丂嶌嬈偼晽偺捠傜側偄丄椓偟偄擔堿偱峴偆丅
丂丂戜栘偼崻偛偲孈傝忋偘丄抾偽偟傪嶍偭偨僿儔側偳偱梒夎傪彍嫀偟丄35乣40搙偺妏搙偱泱幉偺栺 1/2愗傝壓偘傞丅
丂丂曚栘偼巕梩偺侾cm壓傪25乣30搙偱栺 2/3愗傝忋偘傞丅丂愗傝崬傒晹暘偑姰慡偵愙拝偡傞傛偆偵嵎偟崬傒丄愙崌晹傪僋儕僢僾偱偲傔傞丅僋儕僢僾偼桿堷偑廔椆偡傞傑偱丂奜偝側偄丅
丂丂曚栘偺泱幉偼愗傝棧偟傗偡偄傛偆偵戜栘偺泱幉偲棧偟偰丄捈偪偵12cm敨偵敨忋偘偡傞丅
丂丂敨忋偘屻丄姦椻幯側偳偱擔彍偗偟丄暚柖婍側偳偱幖搙傪忋偘傞丅偙偺帪婜偼婥壏偑崅偄偺偱丄傾儖儈忲拝僼傿儖儉側偳偱幷岝偟丄忲崬傑側偄傛偆偵拲堄偡傞丅
丂丂愙栘屻俀擔娫偼幷岝偟丄壏搙乮27亷掱搙乯丄幖搙傪堐帩偟妶拝傪懀偡丅俁擔栚偼擔拞偺崅壏婜偺傒幷岝偟丄彊乆偵擔岝偵姷傜偟偰偄偔丅係乣俆擔栚偐傜搆挿偟側偄傛丂偆偵捠忢偺娗棟偵彊乆偵栠偟偰偄偔丅
丂丂愙栘屻俈乣10擔屻偵丄10杮掱搙偺曚栘偺泱幉傪偮傇偟丄偦偺梻擔偺堔傟壛尭傪尒偰泱幉偺愗抐傪峴偆丅
丂丂泱幉偺愗抐偼曚栘偲搚偑愙怗偟側偄傛偆偵偱偒傞偩偗忋晹偱愗抐偡傞丅
丂
嘑 堢昪娗棟
丂丂泱幉偺愗抐屻丄妶拝傪尒偰敨偢傜偟傪峴偄丄擔岝偵傛偔摉偰傞丅擔拞梩偑偟偍傟傞傛偆側傜幷岝傪峴偆丅
丂丂壏搙娗棟偼妶拝屻偼拫娫24乣28亷丄栭壏12乣15亷傪栚昗偵姺婥偵搘傔傞丅
丂丂偙偺帪婜偵崅栭壏偑懕偔偲庡巬偺帗壴棪偑掅壓偡傞丅偐傫悈偼梷偊丄宻偺懢偄昪偯偔傝偵怱偑偗傞丅
丂丂堢昪擔悢偼攄庬偐傜25擔慜屻偲偡傞丅
丂
(2) 杮傐弨旛
丂丂戜栘偺崻偼巁慺梫媮検偑崅偔丄愺崻惈側偺偱丄桳婡幙傪懡偔娷傒捠婥惈丄曐悈惈偺椙偄搚偯偔傝傪怱偑偗傞丅
丂丂懲旍丄搚忞夵椙嵻偼掕怉侾僇寧慜偵慡憌偵巤梡偟偰丄傛偔峩阆偟偰偍偔丅崅搙壔惉旍椏偼掕怉俈乣10擔慜傑偱偵巤梡偡傞丅
嘆巤旍椺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮kg乛1,000噓乯
旍丂椏丂柤 |
惉丂暘 |
婎 旍 |
懸 旍 |
捛 旍 |
弉 惉 懲 旍 |
丂丂丂 |
3,000 |
丂 |
丂 |
嬯 搚 愇 奃丂 |
丂丂丂丂 |
丂100 |
丂 |
丂 |
俛俵傛偆傝傫 |
侽-20-侽 |
丂丂40 |
丂 |
丂 |
俠俢倀壔惉 |
12-12-12 |
丂丂70 |
丂 |
丂 |
懍岠惈壔惉旍椏 |
16-10-14 |
丂丂20 |
丂30 |
20亊3夞 |
塼旍 |
10-係-俉 |
丂丂丂 |
丂 |
24亊6夞 |
(俶-俹俀俷俆亅俲俀O)
丂 |
丂 |
16-21-15
丂 |
丂 |
丂 |
丂
仸 嬯搚愇奃丄俛俵傛偆傝傫偼搚忞忬懺偵傛傝揔媂挷惍偡傞丅
丂
嘇 悿暆媦傃姅娫
丂丂悿暆180cm丄姅娫70cm丄俀忦愮捁怉丄
丂丂1,000噓摉偨傝1,500姅掱搙偲偡傞丅
丂
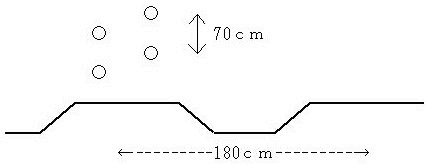
丂
(3) 掕怉
丂丂掕怉偼丄杮梩俁乣3.5枃乮偼庬屻25擔乯偺昪傪梡偄傞丅丂傎応偼掕怉慜擔偵廩暘偐傫悈偟偰偍偔丅崻敨傪曵偝側偄傛偆偵拲堄偟丄敨搚偑 2/3塀傟傞掱搙偺愺怉偊偵偡傞丅怺怉偊偡傞偲曚栘偺帺崻傪敪惗偡傞偙偲偑偁傞丅
丂丂掕怉屻偼廩暘偐傫悈偟丄傎応偺搚偲椙偔側偠傑偣傞丅
丂
(4) 壏搙娗棟
丂丂僉儏僂儕偺惗堢揔壏偼拫娫20乣25亷丄栭娫13乣18亷偱偁傞丅岝崌惉偼屵慜拞偵栺70亾傪峴偆偺偱丄屵慜拞偼25乣30亷丄屵屻偼20乣25亷傪栚埨偵姺婥偡傞丅
丂丂栭壏偺偆偪丄慜栭敿偼岝崌惉嶻暔偺揮棳偑峴傢傟傞偺偱15亷慜屻偲偡傞丅栭敿埲崀偼掅壏偵偟偰屇媧偵傛傞徚栒傪梷偊傞丅
丂丂惗堢慜敿偵崅栭壏偑懕偔偲丄庡巬偺帗壴拝惗棪偑埆偔側傞偺偱姺婥摍偺懳嶔傪偲傞丅
丂丂僇乕僥儞旐暍偼10寧壓弡崰偐傜巒傔傞丅
丂丂壛壏奐巒偼僴僂僗奜偺栭壏偑10亷傪壓夞傞崰偲偟丄11丂寧忋乣壓弡傪栚埨偵偡傞丅壏搙愝掕偼栭壏偱12乣13亷偲偡傞丅偙偺帪婜偼偄偭偨傫庽惃偑悐偊傞偲夞暅偑抶偔丄廂検偵塭嬁偡傞偺偱壛壏偼抶傟側偄傛偆偵偡傞丅
丂
(5) 偐傫悈
丂丂掕怉屻丄妶拝傑偱偼彮検偢偮偺嵶偐側偐傫悈傪峴偄丄妶拝傪懀恑偝偣傞丅妶拝屻偼搆挿偝偣側偄傛偆偵偐傫悈検傪尭傜偟丄崻偺挘傝傪椙偔偡傞丅
丂丂庡巬偺拝壥丒旍戝婜偐傜悈暘梫媮検偑懡偔側傞偺偱丄彊乆偵憹傗偡丅偐傫悈偼揤岓傗搚忞偺幖傝嬶崌偵傛傝挷惍偡傞偑丄姡幖偺嵎偑戝偒偔側傜側偄傛偆偵拲堄偡傞丅
丂丂掅壏婜偵側傞偲偐傫悈偼抧壏偺掅壓丄栭娫偺夁幖偵偮側偑傞偺偱丄岲揤擔偺屵慜拞偵峴偆丅
丂
(6) 桿堷丒揈恈
丂丂杮梩俈乣俉枃崰偵恊偯傞偺桿堷傪峴偆丅庡巬偺壓埵俆愡傑偱偺懁巬偲帗壴偼彍嫀偡傞丅
丂丂懁巬偼侾乣俀愡偱揈怱偟丄崿傒崌傢側偄掱搙偵峴偆丅丂庽惃堐帩偺偨傔丄忢偵俀乣俁偺忋岦偒偺惗挿揰傪巆偡傛偆偵怱偑偗傞丅庡巬偺揈恈偼18愡慜屻傪栚埨偵峴偆丅
丂
(7) 捛旍
丂丂僉儏僂儕偺梴悈暘媧廂偼廂妌奐巒慜崰偐傜媫懍偵憹壛偡傞丅傑偨丄偙偺帪婜偼塰梴惗挿偲惗怋惗挿偑摨帪偵恑峴偡傞偨傔丄憪惃偺堐帩偲廂検妋曐偺偨傔偺捛旍偼抶傟側偄傛偆偵偡傞丅
丂丂侾夞栚偺捛旍偼恊偯傞偺壥幚拝壥旍戝傪妋擣偟偰偐傜丄俶惉暘偱侾乣俀kg傪塼旍偱巤梡偡傞丅憗偡偓傞偲棳傟壥偑懡偔側傞偺偱拲堄偡傞丅
丂丂偦偺屻偼廂妌検偵墳偠偰巤旍偡傞偑丄侾夞偺捛旍偼俶惉暘偱俀kg掱搙傑偱偲偟丄巤旍偺娫妘偱挷惍偡傞丅
丂
(8) 揈梩
丂丂嵦岝偲晽捠偟傪恾傞偨傔丄榁壔偟偨梩傗懁巬偺庴岝傪朩偘偰偄傞梩傪憗傔偵彍嫀偡傞丅
丂丂揈梩偼侾夞偵偮偒俁枃傑偱乮忋丒拞丒壓抜乯偲偡傞丅
丂
(9) 廂妌
丂丂攄庬屻40乣45擔偱廂妌奐巒偲側傞丅奐壴屻俉乣10擔偖傜偄偺庒嵦傝偵怱偑偗傞丅婥壏偑崅偄帪娫懷偺廂妌偼昳幙偑挊偟偔掅壓偡傞偺偱丄屵慜拞偵廂妌偡傞丅
丂
(10)惗棟忈奞偲偦偺懳嶔
嘆 嬋偑傝壥丗姫偒傂偘偲偺愙怗側偳婡夿揑側巋寖偵傛傞傎偐丄姅偺榁壔傗塰梴忬懺丄悈暘忬懺丄捠晽丄擔徠忦審偺埆壔側偳偱傕惗偠傞丅旍攟娗棟傗庴岝懺惃傪堐帩偡傞丅
丂
嘇 尐偙偗壥丗掅栭壏傗僠僢慺夁懡偱惗偠傞丅傑偨丄塰梴忦審偺埆壔偱傕惗偠傞丅
丂
嘊 怟嵶傝丗塰梴忦審偺埆壔傗崅壏丒姡憞丄庴惛忈奞偵傛偭偰惗偠傞丅
丂
嘋 怟懢傝丗庽惃偑棊偪偨偲偒傗丄塰梴晄椙乮僇儕寚朢乯偵傛偭偰惗偠傞丅
丂
(11)昦奞拵杊彍
丂丂導昦奞拵杊彍婎弨偵婎偯偒丄弶婜杊彍偵怱偑偗傞丅
丂
嘆 儀僩昦丗10寧崰偵撥揤柍晽偺擔偑懕偔偲枲墑偡傞丅惗堢屻婜偺旍愗傟傗惉傝旀傟偺帪偵懡敪偡傞偺偱丄姺婥偲丂旍攟娗棟偵拲堄偡傞丅
丂
嘇 奃怓僇價昦丒嬠妀昦丗婥壏偺掅壓偡傞廐崰偐傜敪惗偟丄壥幚偵旐奞傪媦傏偡丅掅壏丒夁幖偑廳側傞偲敪惗偡傞丅滊昦壥幚傗奐壴屻偺壴曎偐傜傕揱愼偡傞偺偱憗傔偵彍嫀偡傞丅栻嵻偺巊梡偵偁偭偨偰偼丄栻嵻娫偺岎嵎掞峈惈偑偁傞偺偱儘乕僥乕僔儑儞巊梡傪椼峴偡傞丅
丂
嘊 偆偳傫偙昦丗崅壏姡憞忦審偱敪惗偡傞丅堢昪婜偐傜梊杊杊彍傪峴偄丄敪惗弶婜偺杊彍傪揙掙偡傞丅懴惈嬠偑敪払偟側偄傛偆偵栻嵻偺儘乕僥乕僔儑儞傪峴偆丅
丂
嘋 儌僓僀僋昦丗傾僽儔儉僔傪夘偟偰揱愼偡傞偺偱丄杊拵僱僢僩側偳偱怤擖傪慾巭偡傞丅
丂
嘍 偦偺懠奞拵丗僴僂僗廃曈偐傜偺旘傃崬傒偑尨場偲側傞偺偱丄僴僂僗懁柺偵姦椻幯摍傪挘傞乮僂儕僲儊僀僈摍乯丅
丂丂傾僓儈僂儅椶丄傾僽儔儉僔椶杊彍偵掕怉帪偵棻嵻傪巤梡偡傞丅丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮崅郪 戩栱丄怷栰 梞擇榊乯