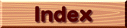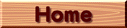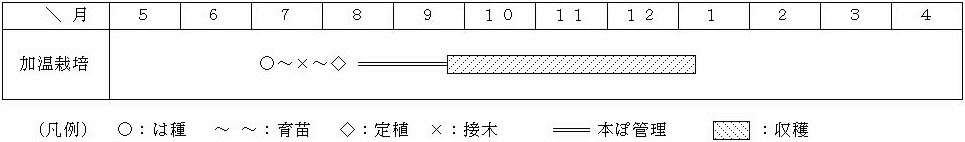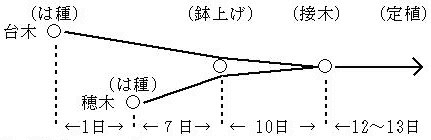1. 品種例 穂木:ハウス桃太郎、桃太郎ヨ−ク
2. 目標収量 8,000 kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
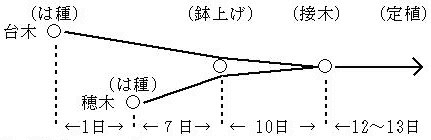
① 育苗床 100 ㎡
② 用土の準備
購入用土 240 リットル (播種床用)
速成床土 3,500 リットル
臭化メチル消毒の後、pH5.5〜6.5、EC0.5に調整する。
速成床土作成例
|
資 材 / 量 |
原 土
|
田 土 1,750 リットル
砂 700 リットル |
肥料等
|
苦土石灰 3.5 kg
過燐酸石灰 7 kg
細粒868 5 kg
|
③ は種
必要種子量は 2,600粒(台木、穂木とも)。水稲育苗箱を利用しては種する。台木、穂木15枚ずつ用意する。 市販の育苗培土を1箱あたり約6リットル準備する。自家 調整する場合は、土、砂、ピートモスをそれぞれ 5:3:2の割合で配合する。
条間5cm、種子間隔2cm程度のすじ播きとし、穂木は台木のは種よりも1日遅らせてまく。
発芽がそろうまでは、育苗箱を新聞紙で覆い、黒色寒冷紗を二重にトンネル掛けして乾燥と温度上昇を防ぐ。
培土の乾燥を防ぐため、発芽まで1〜2回新聞紙が湿る程度かん水を行う。
④ 鉢上げ
12㎝径ポットを 2,350鉢用意し、本葉出葉時に鉢上げする。ポットの中央に台木、端に穂木をそれぞれの茎の太さがそろったものを選んで鉢上げする。
③ 接木(チューブ接ぎ)
台木と穂木の茎の太さをそろえることが肝要である。 接木後活着まではハウスを遮光ネット(遮光率60〜70%)で被覆する。
接木は本葉 2.5枚展開時(穂木播種後約17日)に行い、内径 2.3mmの接木支持チューブを使用する。
台木は双葉の上、穂木は双葉の上をそれぞれ25〜30度に切断する。接木作業は日陰で行う。
接木後3日間は、黒色寒冷紗を二重にトンネル掛けして遮光する。その後1〜2日間、黒色寒冷紗トンネルを一重とする。
湿度保持のため、動力噴霧機により霧吹きを行う(接木当日は1日5回程度、徐々に回数を減らす)。
④ ずらし
接木活着後すぐに3倍の床面積にずらしを行う。
(2) 本ぽ準備
連作ほ場では、太陽熱消毒を施すのが望ましい。
10aあたり稲ワラ2tを施用し、米ヌカ500 kgを散布する。2〜3日湛水状態にした後、ビニールフィルムで全面被覆し、ハウスを密閉し20日放置する。
①施肥例 (kg/1,000㎡)
肥 料 名 |
成 分 |
基 肥 |
待ち肥 |
追 肥 |
熟成堆肥 |
|
2,000 |
|
|
苦土消石灰 |
|
100 |
|
|
BMようりん |
0-20-0 |
40 |
|
|
有機入り化成 |
8-7-8 |
60 |
30 |
|
液 肥
|
6-8-8
|
|
|
150
|
※ 待ち肥は通路に施用する
② 畝立て 裁植密度(2,100株/1,000㎡ )

定植後、地温の上昇を抑さえるため稲わらでうねをマルチする。ポリフィルムの場合は、地温抑制型(白黒タイプ等)を用いる。
(3) 定植
若苗定植(本葉7〜7.5 枚、接木後約18日)とするが、栄養生長過多にならないよう、極端な早植えは避ける。
定植前日、植え床に十分かん水し、涼しい時間帯に定植作業を行う。施設内の温度上昇を抑制するため、活着するまでは不織布等で遮光する。
株 間:25㎝(1条植)、2条植:50㎝
定植後、ホースにより手かん水を行う。
(4) 灌水(かん水チューブ利用)
活着までは十分なかん水を行う(1日5回程度に分け1リットル/株)。活着し、萎れが見られなくなったら、深根にするため4〜5日間はかん水を控える。
以降8〜9月中は、1.5〜2.0リットル/株を3〜5日おきに灌水する。10月以降は徐々に灌水を控える。
(5) 誘引
1条植えの場合、左右に振り分ける。
テープ誘引するが、市販の誘引具で省力化が図れる。
受光確保のため、生育に合わせ、つるおろしを行う。
(6) 通路中耕
1段花房開花時期に通路に施した待ち肥を土になじませ、また通路を平らにする目的で通路を中耕する。
(7) 追肥
第3花房の開花期に急激に吸肥力が弱まる。この時期に必要な養水分が確保できるように液肥で追肥する。
施用時期、量は奇数段花房(3、5、7段)の開花時ごとに 1,000㎡当たり窒素成分3kgとする(液肥は2回に分けて施す)。
(8) 整枝
1本仕立てとし、わき芽は早い目にかき取る。伸びすぎた腋芽を摘むと裂果をまねく。作業は晴れた日に行う。
(9) 着果促進(ホルモン処理、交配バチ)
高温期はマルハナバチの活性が劣るため、9月中旬まで(1〜3段果房)はホルモン処理を行う(トマトトーンは 150倍、トマトラン 1,000倍)。ホルモン処理は花 房あたり4花程度開花した時に1回処理し、空洞果防止にジベレリン5〜10ppmを添加する。
9月中旬以降はマルハナバチを用いる。巣箱の温度上昇防止のため、日覆いをする。
(10)うね間マルチング
9月以降、施設内の湿度上昇防止のため、うね間を切りワラでマルチングする。
(11)摘果
果房当たりの着果数は4〜5果とし、早めに摘果する。
(12)摘葉
各果房の収穫終了後、葉がこみあっていれば通気を促すため、収穫段の下2葉を残し摘葉する。
(13)摘心
8〜9段花房の上2葉を残し、早めに摘心する。
(14)温度管理
11月上旬から18℃を目安に二重カーテン保温を始める。年内穫りの場合、低温期の夜温はやゝ高め(14〜15℃)にし、着色促進を図る。変温管理は下表のとおり。
時刻 |
〜20時 |
20〜22時 |
22時以降 |
日出前1時間 |
温度
|
16℃
|
14℃
|
11〜12℃
|
15〜16℃
|
(15)収穫
高温期はやゝ青め、低温期は赤熟がやゝ進んだ段階で 収穫する。
(13)病害虫防除(県病害虫雑草防除基準を参照すること)
① 青枯病、根腐れ萎凋病(J3)
抵抗性台木を利用する。根腐萎ちょう病(J3)発病の恐れがない場合、アンカーT。J3発病ほ場では、がんばる根に接木する。また、高温期の地温上昇を抑制する。
② 葉かび病
湿度上昇に伴い発病するので、収穫済みの果房より下位の葉が混み合っている場合には、速やかに摘葉する。
③ 灰色かび病
咲き終わった花弁は灰色かび病を誘発するので、開花後の花弁の落ちをよくするため、ホルモン処理は適期の範囲で遅い目に行い、果房処理とする。
また、果実とガクに花弁が挟まっている場合も取除く。
④ 疫病
比較的低温で多湿な条件で発生しやすい。発生を見たら薬剤散布とともに換気に努め、発病葉をちぎり取り、施設外に持ち出す。
⑤ オンシツコナジラミ、タバココナジラミ
黄色粘着板(ホリバー等)の設置は発生の初期には有効である(100枚/1,000㎡)。また、コナジラミ類の発生を確認したら速やかに薬剤防除に努める。
⑥ マメハモグリバエ
苗による本ぽへの持ち込みを防ぐため、育苗ハウス側面を寒冷紗で被覆し進入を抑える。
⑦ タバコガ
施設内への飛び込みを防止するため、施設側面に防虫ネットを張る。黄色蛍光灯も飛来防止効果がある(40W、10灯/1,000㎡)。
⑧ トマトサビダニ
ハウス周辺の除草を徹底する。発病株やハウス内の残渣は焼却するか埋没処分する。
(14)主な生理障害(原因と対策)
① 尻腐れ果
カルシウム欠乏が原因である。着果以降、極端な水分不足にならないよう注意する。
② 裂果
着果後は乾湿差が小さいようにかん水する。
また、側枝除去の遅れも原因となるので、腋芽の除去は早めに行う。
③ 乱形果
多チッ素、多かん水栽培に注意し、過繁茂をさける。
④ 空洞果
高温下でホルモン処理はしない。草勢の低下も一因であり、低温寡日照時期に肥料切れさせない。
⑤ 窓あき果、チャック果
花芽の分化、発育期の障害によるもの。育苗時の過剰施肥、過湿をさける。
⑥ 心止まり
3段花房が開花し、吸肥力のおとろえる時期に窒素切れさせない。
(池田 正彦、住谷 一樹)